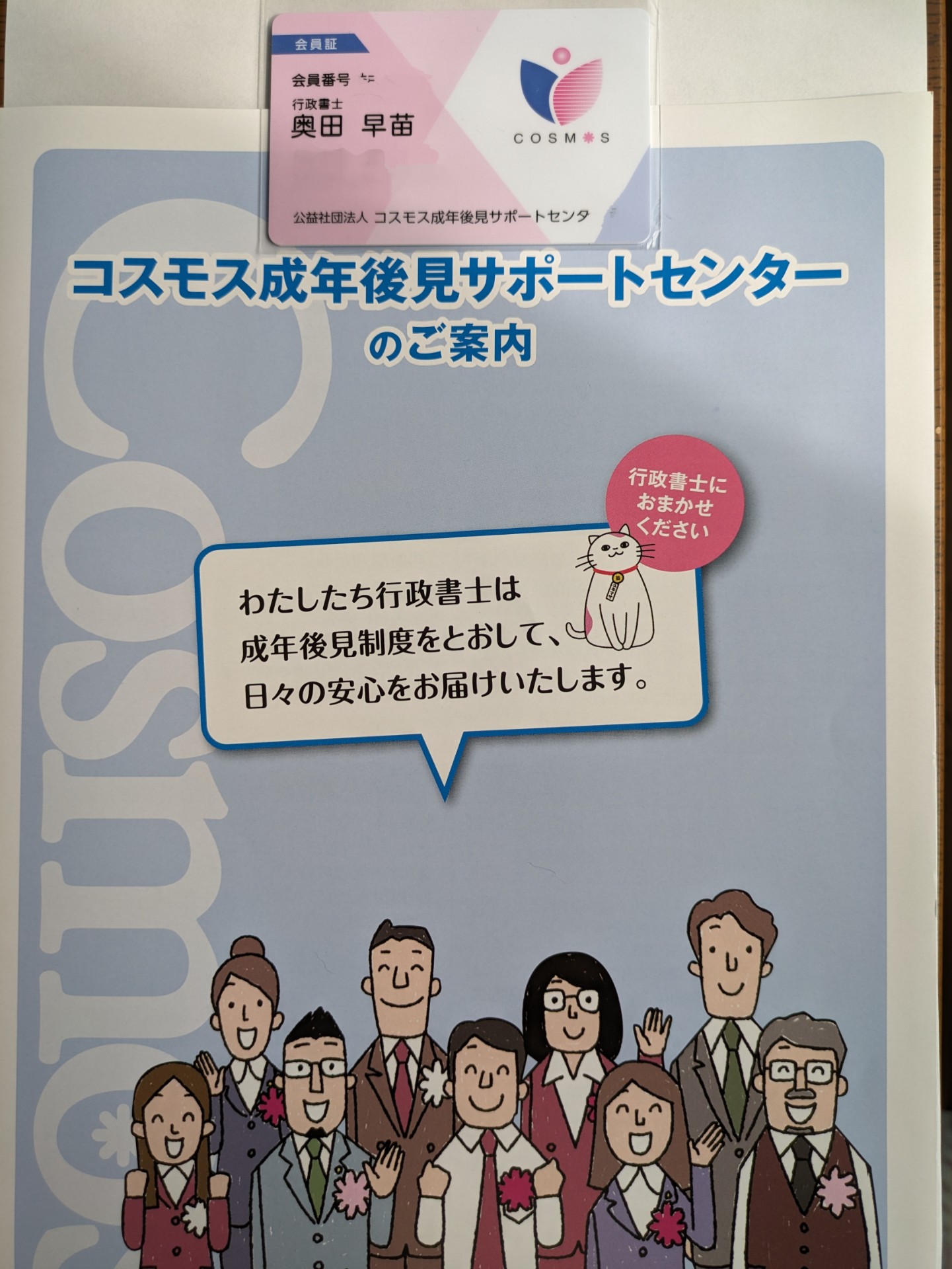「はじめまして、後見人です!」 その④
今回は後見申立てにの際に大きなポイントとなる二つ目、「申立人」についてです。
前回の例を引き続き使い説明していきます。
Aさんの身上監護と財産管理のため、法的な代理人である後見人をつけるとなった場合、家庭裁判所に後見申立てをする必要があります。この「申立てをする人」、つまり申立人は誰が担うのか、がポイントになります。
申立ては、誰もができるわけではありません。例えばAさんの友人や近隣の方が、「Aさんには後見人が必要だから!」と自らAさんの為に一肌脱ごうと考えても、民法に照らすとそれはできません。「民法7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、…の請求により、後見開始の審判をすることができる」(一部を抜粋)と定められています。つまり、Aさんの配偶者か、四親等内の親族、またはAさん自身が申立人となる必要があります。Aさんの場合、四親等以内の親族にあたる、妹さんやそのお子様がいらっしゃいますので、この方々のご協力があれば、民法上申立人になることはできます。しかし、後見の申立ての為の準備は1日2日でできるものでは到底ないのが現状です。まず申立てに必要な書類を揃えるところから始まりますが、前回説明した医師の診断書は絶対ですし、その他に、申立書や申立事情説明書、財産目録、収支予定表などの書類作成が必要で、これらの書類の根拠となるような公的な書類(例えば、戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明、通帳のコピー等)を関係機関に請求する必要もあります。私は一度、私の父親の為にもし申立てをするとしたら、という前提で書類を作ってみたのですが、その膨大な量に心が折れそうになりました。また、自分の父親のことはたいてい分かっているから大丈夫と軽い気持ちで書き始めたのですが、学歴や職歴など過去の細かい経歴にまで触れる必要があり、また父の財産の内容や普段の生活における収支なども把握しきれておらず、これを申立人一人でこなすことは無理だと感じました。そして申立ての為には決められた手数料を支払う必要もあり、お金がかかります。前後しますが、申立ての為の書類作成や申立ての手続き自体を専門家に依頼すると数十万円の報酬もかかってきます。申立の際に、これらの費用をAさんの財産から支出することを請求する旨を付記することはできますが、申立人の心理的、物質的な負担はやはり大きくなります。
また例えばAさんに親族がいたとしても、様々な事情からAさんとの関りを拒まれ、申立人にはなりたくないという方もいらっしゃるかもしれません。では、Aさんに四親等以内の親族がいない場合はどうなるのでしょうか。実は申立ての中には、「首長申立て」というものもあります。これは本人の居住する市町村長が公の立場で申立人となるものです。市町村ごとに首長申立ての対象になるかの条件は異なりますが、実は令和5年度の申立のうちの約23%がこの首長申立て案件になっています。要因は様々考えられますが、おひとりさまの高齢者の増加、親族関係の希薄化などが挙げられます。
本人の身上監護、財産管理の為に後見申立てが必要となった場合、申立人が必ず必要となりますが、その役目を誰が担うのか、は大きなポイントです。
今回は前回に続き、後見の申立てから選任までのうち、「申立におけるポイント」のお話でした。
次回は、「はじめまして、後見人です! その⑤ 後見人には誰がなる?」のお話です。