About us
医療従事者から街の法律家へ
最期の時に寄り添ってきたからできる終活サポート
医療従事者として病院や高齢者施設で働く中で、超高齢社会において、「その時に、備える」ことの必要性を実感してきました。
「いつかはその時が来ると分かっている」「そろそろ考えなければいけないと思っている」
だけど…生きているうちに最期や亡き後について話題にするのは不謹慎!まだまだ元気だし、淋しいことや悲しいことは想像できない、したくない。
とてもデリケートで内面的なことだから誰かに話すもの躊躇してしまう。
そんなお気持ちに寄り添って終活のお手伝いをさせていただきます。
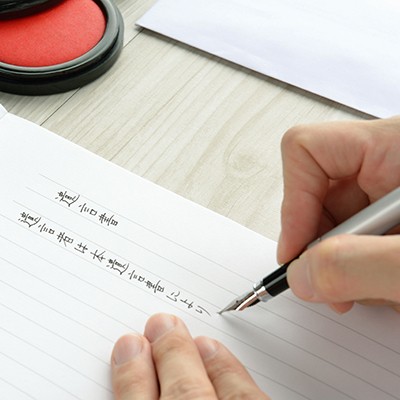

医療従事者の視点
医療従事者として現場で見て・感じてきた視点から、老後や最期に対する不安やお悩み事のその先まで汲み取れるような行き届いたご対応をさせていただきます。

良き相続相談者として
ご家族やご自分の老後や最期を想像し、その時に対する備えをしていくことは、時に心理的なご負担をともないます。相談しにくい内容だからこそ良き相談者としてお話をお伺いさせていただきます。

稲沢市から愛知県全域まで
地域に根差したお付き合い
愛知県稲沢市を拠点に、地元の皆様に寄り添う地域中心とした終活・相続のお手伝いをさせていただきます。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話もしくはメールフォームからご相談内容をお伝えください。
ヒアリング(無料相談)
ご予約の日に、具体的な内容をヒアリングさせていただきます。
お見積
ご相談内容に合わせてお見積書をご提示させて頂きます。
ご契約
お見積内容にご納得いただけましたらご契約となります。
業務着手・遂行
書類作成・調査・各種サポートを進めさせていただきます。
業務完了・納品・報告
完成した書類や報告書をお渡しさせていただきお支払となります。
お役立ちコラム
-
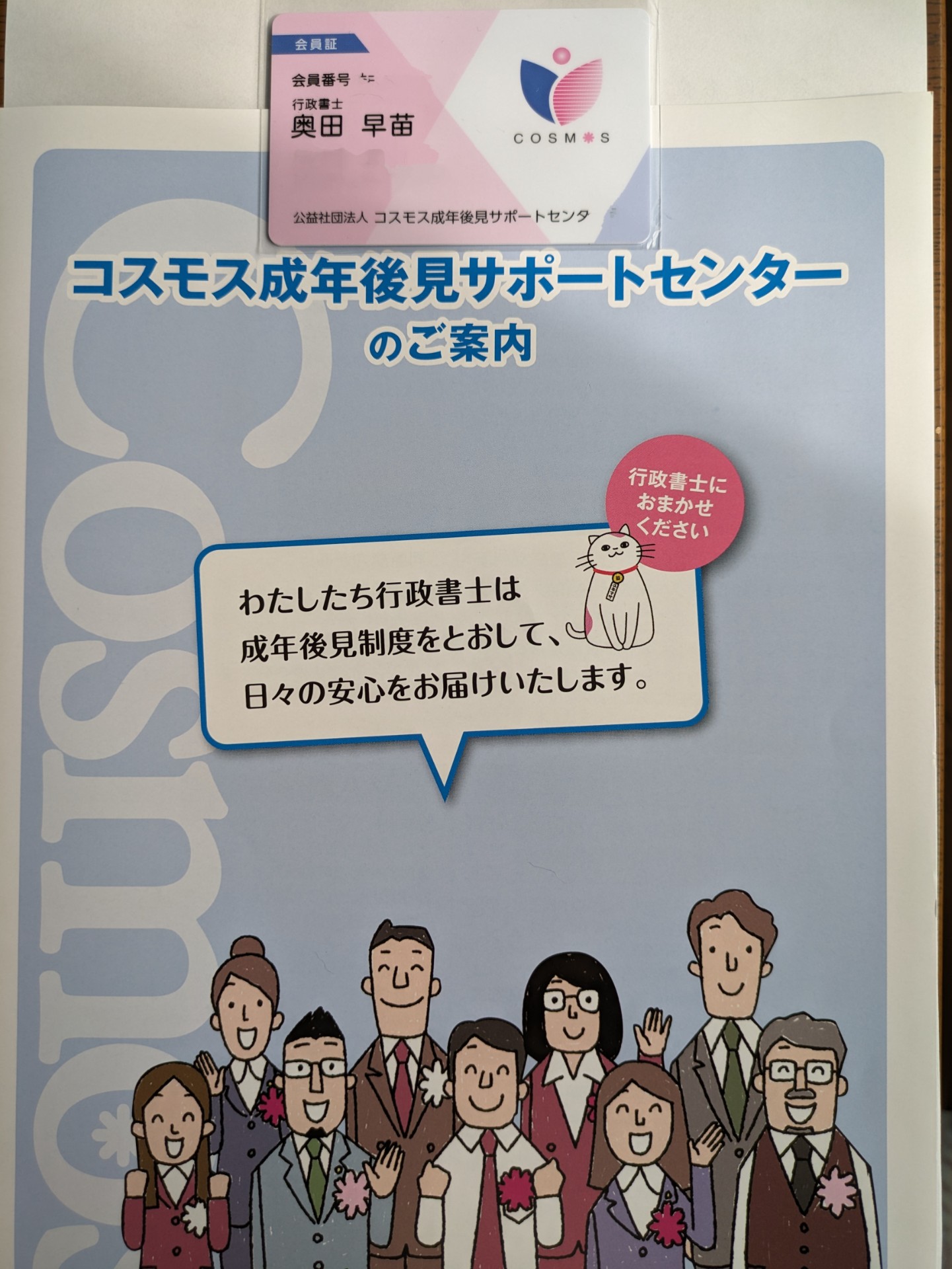
- 後見制度は悪法?
- 先日のこと。普段からお世話になっている介護福祉関係者の方から連絡をいただきました。<div>この方が担当されている利用者様に協力していただける親族がおらず、後見人をつけるしかないという話が出ているが、「後見って悪法ですよね、だからできたら使いたくないんです」と。</div><div>このようなご相談を受けることは少なくありません。行政書士で組織するコスモスあいちの会員として普段後見業務をやらせていただいている私としては複雑な気持ちにもなりますが、実はこういったご相談は、後見制度を正しく知っていただくチャンスでもあるととらえています。</div><div>話は戻り、この方に「どうして後見は悪法だと思うのですか?」と聞くと、こんなお返事がありました。</div><div>「後見人はお金のことしか考えていないと聞いた」「本人に会いにも来ないと聞いた」「本人が亡くなると本人の財産を全部持っていってしまうと聞いた」などなど…。たしかに、この話だけ聞くと、後見は悪法、後見人は悪人と言われても仕方ないかもしれませんね。ただ、後見人としてきちんと正しくご説明し、誤解を解きたいことも多くあります。</div><div>・「後見人はお金のことしか考えていない」→後見人は本人の財産をお預かりし、本人の命や生活、人生を守るためにお預かりした財産を維持・管理・処分していきます。<br></div><div>・「本人に会いにも来ない」→少なくとも私や私の知っている後見人は、定期的に本人を訪問、面談し、衣食住に困っていないか、虐待等を受けていないか等の確認を身上監護の一環としておこない、また、関係者との連携を図っています。</div><div>・「本人が亡くなると後見人が財産を持っていく」→本人が亡くなったと同時に後見人は辞任となり、お預かりしていた財産は本人の相続人がいればその相続人に引き渡します。</div><div>いかがでしょうか、明確に誤解されているものもありますが、聞き方やとらえ方によっては確かにそう思われても仕方ないかもしれないというところもあります。</div><div>情報社会となった今、ワンクリック、ワンタップで得られる情報は無限にあり、私達の生活を豊かにしてくれるものもたくさんありますが、反対に正しい情報と誤った情報とを見分けるのがとても困難になっていると感じます。この方の場合も、ご自身はまだ後見人が就いている方を担当したことがないとのことで、後見について色々調べてみたけれど、どれも批判的な情報ばかりだったからとのことでした。そして私が一通りご説明したことに対し、「知っておくことも必要だけど、正しく知らなければ、せっかくある選択肢を自ら潰してしまうことにもなるんですね」と仰っていただくことができました。私にとっても、この方が、目先の情報だけにとらわれず、声をあげて質問してくださったことは意義のあることだったと感じております。</div><div>超高齢社会において、高齢者を支援するにはチーム一丸となることが必要だと思います。そして後見人もそのチームの一員として、本人に代わって法律行為を通し財産管理や身上監護をしてまいります。ぜひ後見人を身近に感じていただき、そのチームに入れていただきたいと思います。</div>
-

- 人生の大先輩から学ぶこと
- <div>(※写真と本文の内容とは関連ございません)</div><div><br></div>つい先日のこと。認知症症状のあるA子さんと並んでテレビでニュースを見る時間がありました。<div>今、ニュースで報道されない日はないのではないかというほど深刻な社会問題になっている特殊詐欺。A子さんと見ていたニュースでも、特殊詐欺により多額の預貯金を騙し取られた高齢の男性の被害の実態が流れました。手口は本当に悪質かつ巧妙。被害に遭われたご本人の心情を思うと、心底怒りがわいてきます。「他人様のことをどう思っているんだろうね、許せんわ!」と思わずつぶやく私。隣のA子さんには伝わらないだろうなあと思っていると、なんとそのA子さん、私のつぶやきに続いてこんなことを仰ったのです。</div><div>「こーんなくだらんことに頭使うくらいなら、もっと世のため人のためになることに頭使わなかんわ!とろくさい!!」 (とろくさい、というのは尾張弁なのでしょうか、ばかばかしい、呆れてものが言えない、というニュアンスで使っています) </div><div><div>そう、A子さんは、特殊詐欺の犯人にモノ申しているのです。人を騙してお金を搾取する方法を考える知恵があるのであれば、もっと良いことにその頭を使え、世のため人のために知恵を絞れ、と。</div><div>実はA子さんは元々、こちらから問いかけや声掛けをすればお返事をするという控えめな方。ご自分から声をあげたり、感情を出されるような方ではありません。しかし、この時は違いました。隣で聞いた私は目が点…A子さんの方を見ると、その目は真剣、怒りの表情。認知症であることなどすっかり忘れてしまいそうな勢いです。 </div><div>私はA子さんの言葉に感心すると同時に恥ずかしさと申し訳なさでいっぱいになりました。A子さんは認知症だから伝わらないだろうと勝手に決めつけていたからです。でも実際のA子さんは違いました。どこまでこのニュースの実態をご理解されたのかは分かりませんが、少なくとも「人を騙すこと」は悪いことで決してやってはいけない、騙す知恵があるのであれば人の役に立つことに使え、と仰ったのです。</div><div>長年看護職としてご高齢の方に接する機会をいただいてきましたが、その中で認知症と診断された方でも、相手の表情やしぐさを読み取る、感じ取るというところでは、こちらが驚くほど敏感で繊細な感性を保たれる方は多いと感じます。ケア中にふと考えごとをしてぼんやりしていると、「あんた、頑張りすぎちゃいかんよ!」と肩をもんでくださったり、マスク越しに小さくため息をつくと、「迷惑かけてごめんね」と謝られてこらたり。こちらが無意識にとっている行動で心の中を見透かされているように感じます。これはきっと人生において長い長い時間とたくさんの経験を積み重ねられてきたからこそのなせる技、たとえ認知症になったとしても失い切ることのない本能のようなものではないでしょうか。</div><div>仕事と家庭の両立や職場の人間関係で悩んだ時、人生の大先輩方を前にすると、「この方にも同じように悩んだ時があったのかな。それを乗り越えてきたんだな」と思い、「私なんてまだまだヒヨッコ!大丈夫、私にもできる!」と不思議なパワーをもらえる気がします。</div><div>A子さんの言葉に、人生の大先輩から学ぶことはたくさんあるのだとあらためて気づくことができました。</div></div><div>人間、歳をとらない人はいません。しかし、年齢の積み重ねと同時に、様々な出会いや経験も積み重なっていきます。</div><div>まだまだ若輩者の私ですが、いつかは誰かの人生の大先輩として何かを残したり伝えられるような存在になれることを目標にしたいと思います。</div>
-

- 「当事者」になって気付いたこと
- <div>※写真は本文の内容とは関連ございません。</div><div><br></div><div>私事で恐縮ですが、4月にくも膜下出血を発症し、2か月ほど療養期間をいただいておりました。幸いにも発見と治療が早く、現在は後遺症もほぼ消失しスローペースではありますが仕事に復帰しております。治療にあたってくださった主治医の先生と医療従事者の皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。</div><div>決して愉快な話題ではないのですが、ようやく振り返る心の余裕ができましたので、今回の出来事を通して私と私の家族との間で再度考え直すきっかけとなったエピソードを紹介させていただきたいと思います。</div><div>私は3年前に「リビングウィル」を記しました。私は、万が一命の瀬戸際に立たされたとしても、ただ生命を生きながらえさせる目的だけの措置は受けず、時間の経過とともに自然な形で心臓が止まるのを待って死を迎えたいと望んでいるため、それを意思表示したのです。今回医師から病名を告げられた時、意識はしっかりあったものの、看護職の知識と経験から、「私、このまま死ぬかもしれない」と、静かに覚悟を決めました。そして付き添ってくれていた主人にとっさにこう言いました。「もし私に万が一があったら、(リビングウィルを示した)あのカードを先生に見せてね」と。主人は私に動揺を見せまいといつもと変わらない表情で、「分かったから、今は何も心配しなくていいから」とだけ答えてくれました。この後私は入院することになったため、自宅ではしばらく主人と次男の二人となりました。私が入院し主人が帰宅してすぐに、私の記したリビングウィルと、「延命はしない」という希望について、二人で夜中まで話し合ったそうです。私がリビングウィルを記していることは二人とも知っています。その上で、主人は私の意思を尊重してやりたいと次男に話したところ、次男は、「とても受け入れられないから、考え直す時間が欲しい」と訴えたそうです。入院した翌日、次男がお見舞いにきてくれました。病室の扉が開き、私と目が合った途端、次男は泣き出しました。おそらく心配で不安でいっぱいだったのだと思います。(私も母に対してそうですが、自分の母親は不死身、のように感じていたのでしょう。子供から見たお母さんって、いつも元気でチャキチャキしているイメージありますよね、個人的な意見ですが(笑))しばらくして落ち着いた次男からこんなことをお願いされました。「お母さん、お母さんが延命を望まないってことは知ってるんだけどさ…、あれ、ちょっと考えさせてくれないかな」 私は、私の意思であるならば、おそらく家族は反対はしない、従ってくれるだろうと思っていました。次男も私がリビングウィルを記した当時はそう思ったそうです。しかし、主人から私が入院したことや病名、延命は望まないと言っていることなどを聞き、このまま私が死んでしまったらとても受け入れられない、どんな形でもとりあえずは生きていてほしい、生きてそばにいてほしい、と心から思った、と泣きながら伝えてきたのです。これには私も泣きました。たった一晩で次男が私の命についてこんなにも考え、思ってくれたということに、うれしさと申し訳なさといっぱいになりました。同時に、自分の記したリビングウィルは、ひとりよがりの意思表示だったのではないかと深く反省しました。今回のようにその日の朝まで元気だった母親が夜には命の瀬戸際にいる、その状況で、「私は延命措置は希望しないから何もしないで死なせてね」の言葉を聞いていたからといって、「はい、そうしましょう」とはならない、なれない、と。もし私が家族の誰かと反対の立場だったらどうか…と。</div><div>私は終活のご相談を受けた時に、「一番考えていただきたい終活の一つ」として、命の瀬戸際に対する備えについてご説明しています。「命に正解も不正解もない、人によって死生観は違う、今すぐにどうしたいかを決めて形にして残す、ということは難しいこと。でも、だからこそ、折に触れて、「考えること」「想像すること」「声をあげること」をしていただきたい」と。今回の出来事はまさに自分自身に再度この説明を投げかけることとなりました。「私の命は、私が決める」だけではなく、「大切に想ってくれる人がいる私の命だから、じっくり一緒に考えてもらう」ことも必要だと身をもって感じました。</div><div>まさかの病気をし、家族にも心配をかけましたが、自分自身の命と改めて向き合うきっかけを作ってもらったと感じます。一日一日を大切に、そして感謝の気持ちを忘れずに、日々精進してまいります。</div>
お知らせ
- 2026年01月05日 09:26:00
- ごあいさつ
- 2025年11月28日 09:45:00
- お気軽にご相談ください
- 2025年09月12日 10:24:00
- Neoふくじま行政書士事務所第4回座談会へのご参加、誠にありがとうございました!
- 2025年08月22日 07:53:00
- 第4回座談会のお申し込み期限が近づいてまいりました
- 2025年08月08日 11:57:00
- 第4回座談会を開催させていただきます!



