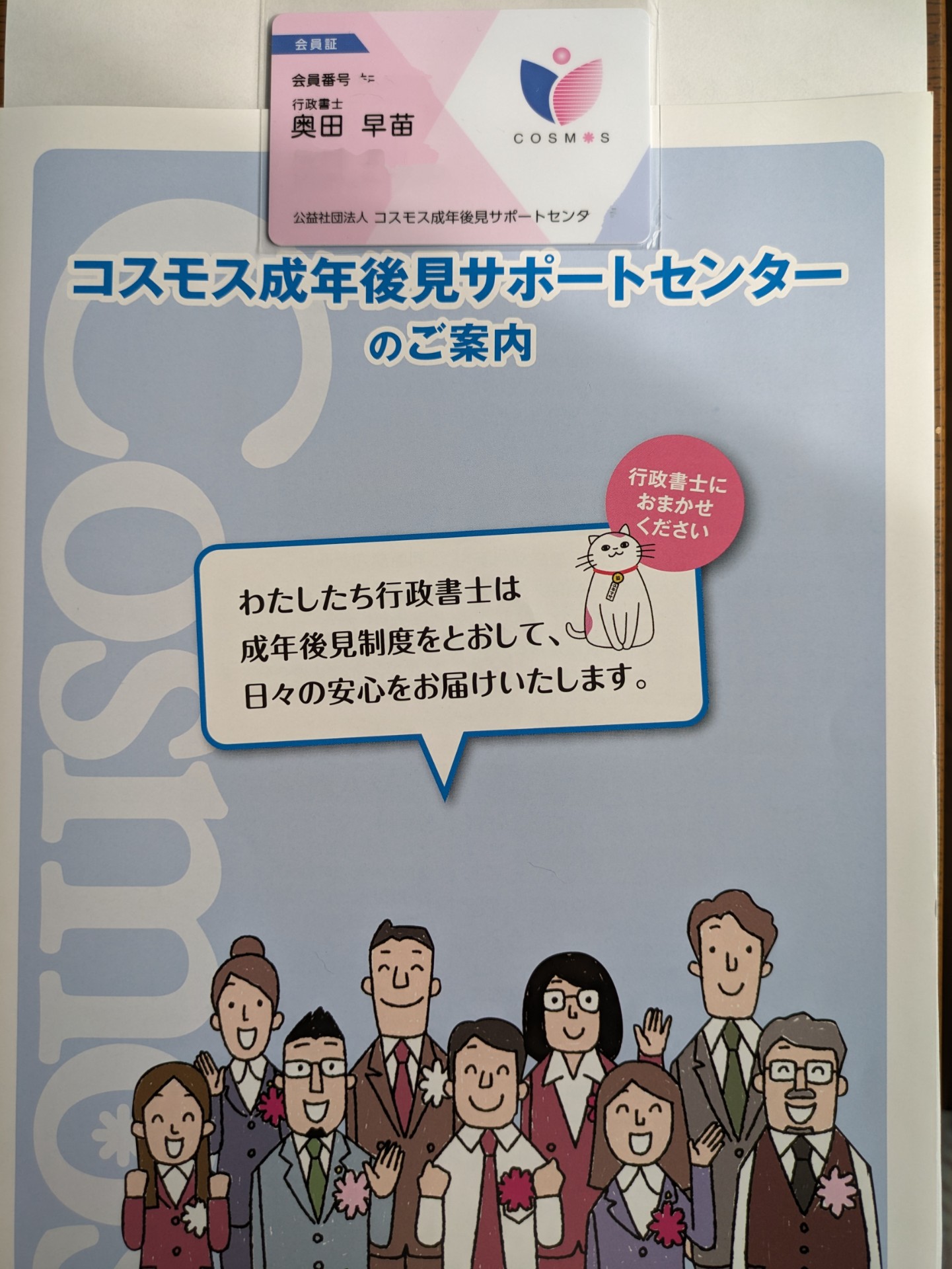「はじめまして、後見人です!」 その③
今回は、後見の申立てから選任まで~後見申立てのポイント~を説明したいと思います。
分かりやすく、「認知症を患い、おひとり暮らしが困難となった高齢者のAさん」を例にあげてご説明します。
Aさんは長年ご自宅にておひとり暮らしをされてきましたが、今回友人の一人からご様子がおかしいと行政に情報が寄せられ、調査の結果、認知症様の症状がかなり進行しており、すぐにでも公的な介護福祉支援を受けることが望ましく、また、自宅を含めた不動産や預貯金といった財産の管理も必要であることされました。Aさんには結婚歴がなく、お子様もおらず、妹さん(以下Bさん)がいらっしゃいますが遠方に住んでおり、Bさん自身も高齢で家族からの介護を受けており、すでにAさんのお世話をすることが困難な状況、Bさんにはお子様がいらっしゃいますが、とてもAさんの介護まで担うことはできないとの回答でした。こうなると、Aさんの身上監護、財産管理をAさんやAさんの家族親族に代わって行う後見人の申立てをすることを検討する必要が出てきます。
申立てをするのにまず必要になり、かつ大きなポイントになるのが、
1「医師の診断書」と、2「申立人」です。
今回は1について。
後見の申立てに必要になる書類は膨大にあります。申立書の書式は決まっていますが、それに添付する書類も官公署に請求したり、自ら作成したりする必要になります。その添付書類の中で、絶対に外せないのが、「診断書」です。逆にいうと、この診断書がなければ、申立てはできません。(家庭裁判所に受理されません)
ではこの診断書を書くのは誰か?当然「医師」になるのですが、このAさんの場合、「認知症であることが原因によって意思能力や判断能力を欠いている」という診断がされる必要があります。医師は精神科や神経内科など頭や心を専門にする医師でなくても構いません。最初に相談すべきは、やはりかかりつけ医です。しかし、ここで時々思わぬ壁にぶつかることがあります。あくまでも私の経験ですが、医師に診断書を依頼したが、「(診断書を)書けないと言われてしまった」という相談を受けることが時々あるのです。「うちは内科だから認知症かどうかの診断はできない」「検査ができないから」という実質的な理由なこともあれば、「この人は後見をつけるような重度の認知症ではないから」という判断や診断に基づく理由をあげられることもあります。私も長年医療の現場で働いてきましたが、後見申立てに関する診断書に限らず、医師が診断書を書く、ということは、大きな判断と責任をともなうことになります。私が以前に働いていた医療機関の院長は「診断書は医師の「全て」を込めて書くもの」と仰っていました。専門知識をもって書いた1枚で、その患者さんの権利や義務が確定し、生活や人生を変えることもある、だから真実しか書けない、と。先ほども触れた通り、家庭裁判所は、Aさんに後見が必要かどうかまず医師の診断書を参考にします。申立てを経て後見人がついた場合、後見人には大変大きな権限や裁量が認められ、たとえAさんの家族や親族でも、後見人を無視してAさんの身上監護や財産管理を行うことはできません。そうなると、ケースによっては、最初に診断書を書いた医師が家族や親族から思わぬバッシングを受けることにもなりかねないのです。(そんなことがあってはいけないと個人的には思うのですが)
医師の診断書を用意することは、申立には絶対条件になりますが、様々な事情、状況から、書いてもらえない、または書いてもらえる医師がいない、という壁にぶつかることもあるのが現状です。
今回は後見申立て時のポイントとして、「医師の診断書」をあげました。次回は申立て時のポイント、2申立人にフォーカスしたいと思います。