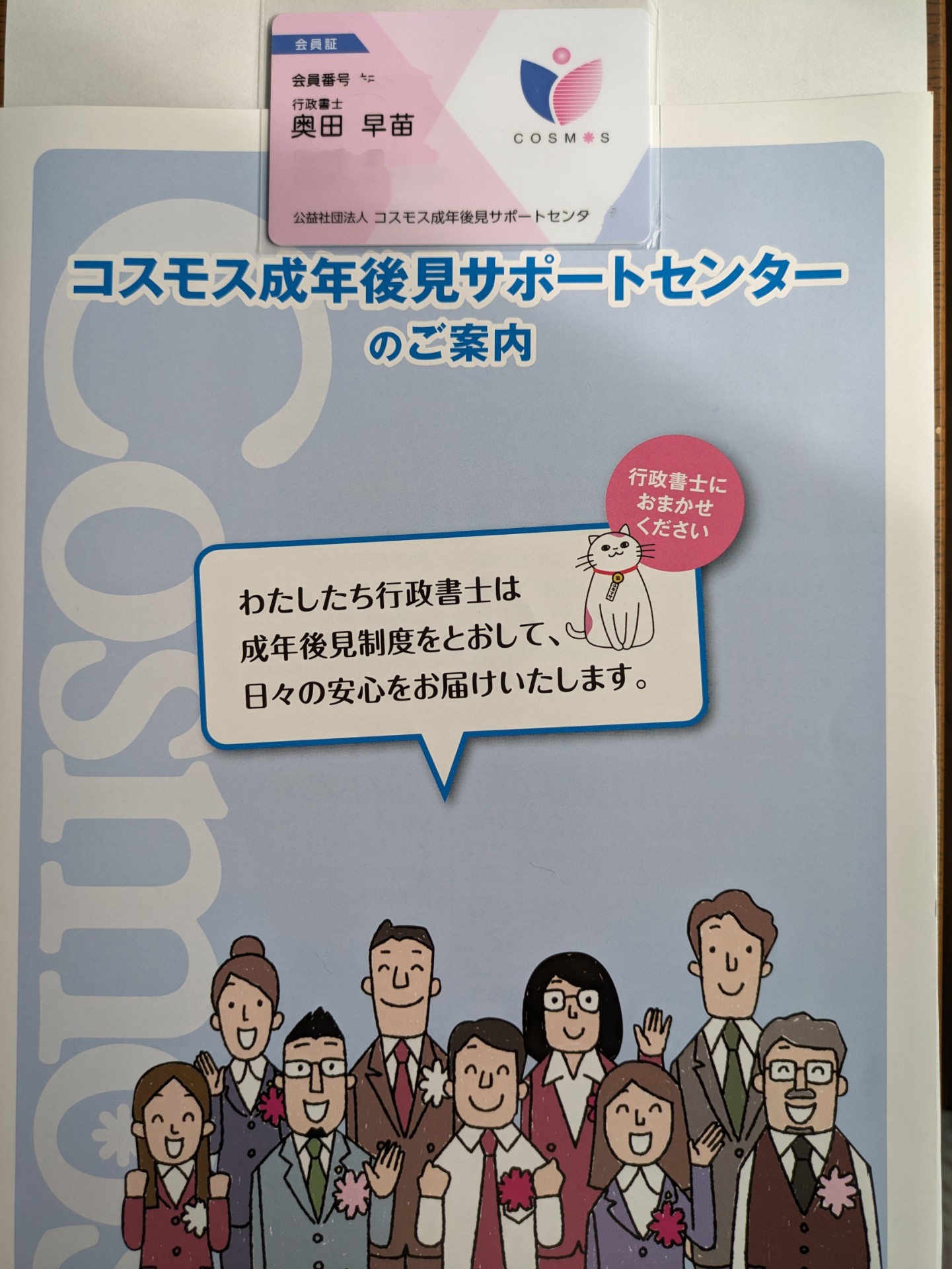「はじめまして、後見人です!」 その⑤
今回は、テーマ「はじめまして、後見人です! その⑤ 後見人には誰がなる?」です。
前回までのお話で、申立までの流れや必要事項などをご説明しました。
それでは実際に「後見人」とよばれる人には誰が選任されるのでしょうか。
先のお話でも書いた通り、後見人には非常に重要な権限があります。後見人は被後見人(後見を受ける方)に必要なあらゆる法律行為を代理人として行い、また、被後見人が行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為をのぞく)を取り消すことも可能です(民法9条、120条1項)この権限のもとで、意思能力・判断能力を欠く状況にある方の生活や人生(身上監護)、財産(財産管理)を守る必要があります。ですので、後見人は誰でもよいというわけにはいかず、家庭裁判所によって選任されます(民法843条1項)。逆にいえば、「この人に後見人になってほしい」「私が後見人になりたい」と希望し、申立ての際に「候補者」として挙げても、家庭裁判所がその通りに選任しない可能性もあるということです(民法843条4項)。
実はこの点は、この法定後見制度が使い勝手が良くないと言われる理由の一つになっていると個人的に考えています。のちに被後見人となる方のご親族等からすると、選任された後見人が全く面識のない相手だったとすると、「思いもよらない人に(被後見人の)財産を取り上げられてしまった」「自分たちがいるのに、何もやらせてもらえない」などという不信感を持たれるケースも少なくないのです。特に申立人となった方が、自らを後見人候補者として申立てを行った場合に、自分ではなく全く知らない人が後見人に選任されたとするとどうでしょうか。自分が後見をやれないことに加え、どこの誰だか知らない人に被後見人の財産を預けなければならないとなると、かなりの心理的負担が生じるのではないかと思います。選任された後見人が気に入らないからという理由では、後見の申立てを取り下げることはできません。そもそもご本人(被後見人)が意思能力・判断能力を欠く常況であることを理由に後見人が必要である、と申立てがされているので、家庭裁判所が後見人が必要と判断したのであれば、取り下げはできないのです。
(ただ、選任された後見人に後見業務において不正行為があった場合等には親族等からの請求や家庭裁判所の職権により後見人が解任される可能性もありますし(民法846条)、後見人側の事由により家庭裁判所の許可を得て自ら辞任することも可能(民法844条)です)後見開始の審判が下ると、基本的には被後見人が亡くなるまでの間、半永久的に後見人が就き続けることになります。つまり、申立のきっかけとなるような出来事がたとえ解決、終了したとしても(たとえば不動産の売却や預貯金の解約等)、後見人による後見業務は継続します。
私も行政書士で組織するコスモス後見サポートセンターの会員として後見業務にあたっており、案件によっては申立ての段階からご本人やそのご家族、介護福祉関係者の方と接する場面も多いのですが、申立ての際に、候補者として名前を挙げていただくことはできても、実際に選ぶのは家庭裁判所になります、と丁寧にご説明させていただいております。また、実際に選任されたとしても、後見開始の審判が確定がされるまでは、業務を開始できない旨も重ねてご説明しております。
しかし、「どこの誰が後見人になるか分からない」と聞くと、そもそもこの制度を使うということに消極的になられる方も多い印象です。後見人による被後見人の財産の横領等の不正行為も社会問題として取り上げられることもある中で、後見人と被後見人との間、また、後見人と被後見人を取り巻く関係者の間、で信頼関係を構築していくか、がとても大きな課題になると考えます。
今回は後見人には誰がなる?のお話でした。次回は後見業務の実際についてのお話になります。