コラム
-
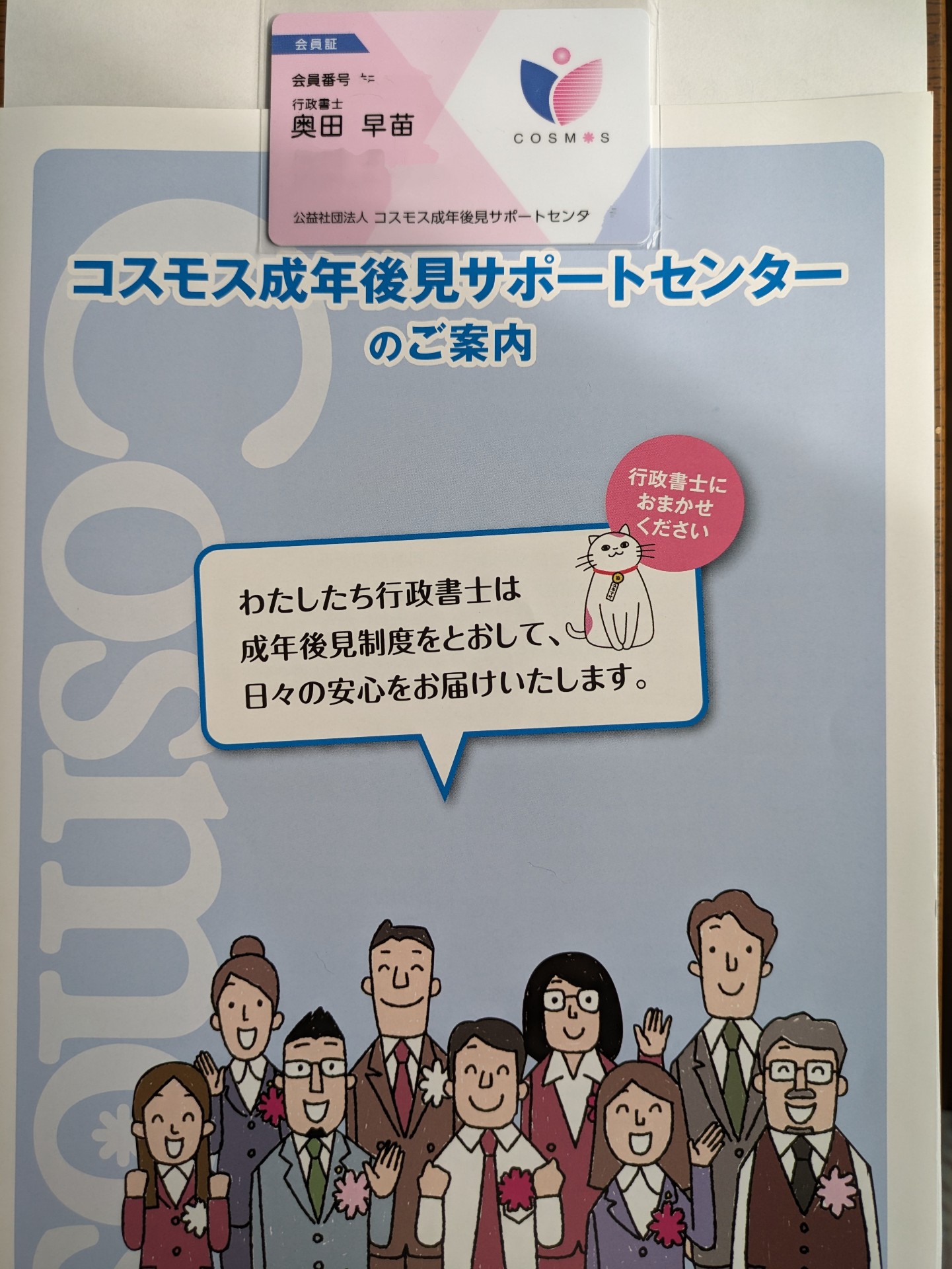
- 「はじめまして、後見人です!」 その①
- 私事ではありますが、今年3月に、行政書士で構成する団体である「コスモス成年後見サポートセンター」に入会いたしました。この団体は、成年後見実務についての研修を通じ会員の資質向上に努め、業務管理等を通じて会員の指導・監督を行う組織で、後見業務を行うのにあたり定期的に業務報告をしたり、コスモスが開催する研修会や相談会に参加したりなど、コスモス会員は団体(以下、「コスモス」と呼びます)のもとで日々後見業務にあたっています。<div>皆さん、「後見制度」や「後見人」という言葉をお聞きになったことはありますか? セミナーや座談会でこの質問をすると、ほとんどの方から「何となく聞いたことはある」というお返事があります。もう少し深く、「では実際に、後見人と呼ばれる人とに会ったことがある、後見人がついているという人が身近にいる、という方はいらっしゃいますか?」と伺うと、今のところそのような方がいらっしゃったことはありません。後見という制度があることは何となく知っている、聞いたことはあるけれど、実際にどんな仕組みなのか、後見人とはどんな人なのかまでは分からない、知らない、という方は少なくないのではないでしょうか。私は前職が医療関係ということもあり、看護・介護・福祉関係の知人・友人も多いのですが、その知人・友人に聞いても、「詳しくは分からない」と言われることが多いです。実際に私も長年現場で働いてきましたが、「今思うと、あの患者さんに時々面会に来ていたのは、ひょっとして後見人…だったのかな」と思い出せる方が一人いる程度です。それくらい、医療や介護福祉の現場で働く人にとっても、なかなか馴染みがないのが現状です。この後見制度に関する法律は、実は今から20年以上も前の2000年に施行されています。この時同時に施行されたのが「介護保険法」であり、この二つの制度は「車の両輪」と呼ばれています。しかし、現在の介護に関する制度とともに発足したのにも関わらず、介護に関する知識や情報の広がりよりも、後見に関する知識や情報の広がりは遅れをとっていることを、個人的ではありますが、実感しています。そして、この知識や情報の少なさが、巡り巡って、後見制度を使った支援を必要とする方、つまり、被後見人の支援の遅れにつながるのではないか、と考えます。では、なぜ後見制度はなかなか周知されないのか? これはあくまでも私の意見なのですが、「知るきっかけ・機会がない」ことが一番大きな原因ではないかと考えます。今後の記事でもう少し掘り下げてお話していきますが、いうまでもなく、超高齢社会にある今の日本で、介護が必要な方の割合も増加しています。 そして、法定後見の申立て件数は年々増加傾向にあります。しかし、そんな状況の中で、介護を担う医療・介護福祉に携わる人手は、圧倒的に不足しています。「常に人手不足」「求人をかけても応募がない」という話も日常的に耳にします。そんな日々の業務をこなす、回すだけで手いっぱいの中で、医療や介護に関する法律や仕組みを学ぼうと思っても、時間がない、余裕がない、というのが、現状なのです。(私も実際に、いくつかの高齢者施設様に、後見についての座談会をやらせてくださいとお願いにあがったのですが、「これからニーズが高まる制度でしょうし、必要なことだとは思うのですが、なにぶん時間的にも人員的にも余裕がなくて…」と丁重にお断りされることがほとんどです。) </div><div>現在コスモス会員として後見業務にあたっていますが、「後見制度を知っていただく」ことも必要な業務の一つだと考えています。制度自体が複雑な部分も多く、とっつきにくいのですが、少しでも分かりやすく、身近な制度の一つとしてとらえていただけるよう、このシリーズで順にお話していきたいと思います。</div><div><br></div><div>次回「はじめまして、後見人です! その②」に続きます。</div>
-

- 「終活」って何すること? ~ その④ 実はこんな現実が。介護が必要な状態になった時に備える ~
- ※写真と本文の内容とは、関連ございません。<div><br></div><div>これまで3回にわたり「終活」って何すること?をテーマに書かせていただきました。今回はその④、最終章になります。</div><div>その①でご説明した通り、分かりやすく順に時間と状況を巻き戻してお話してきましたので、今回は、「今この瞬間に最も近い時間帯の終活」ということになります。人生100年時代、医療や福祉の技術が進み、日本人の平均寿命も男女ともに80才を超えています。「人間、死ぬが死ぬまで、自分のことは自分で。誰にも迷惑かけたくない」というのは一番の理想であり、どなたもが望むことです。しかし、実際はそうではないことも多いのが現実です。「誰かの世話にならなければならない」状態になる原因やリスクは、年齢を重ねるほど高くなります。病気やけがによる体の不自由ももちろんですが、皆様にとって一番身近で一番心配なのは、「頭の不自由」、中でも認知症ではないでしょうか。認知症と一口で言っても、実は種類があり症状も色々ですが、認知症が一定の度合いで進行した場合、日常生活の中で様々な問題や課題が出てきます。実例を挙げてみると、「不要な物を不当に高額な値段で売りつけられても、それが良いか悪いか判断できず、言われるがまま契約してしまう」「清潔を保つ行為(入浴や着替えなど)ができない」「近所を徘徊し、交通事故に遭ってしまった」など、大切な財産を失ったり、命や生活が危険にさらされることにつながります。この実例を踏まえるともし万が一皆様の近しいご家族が認知症になった場合、どのような支援や援助が必要になるでしょうか。まずはその方に適切な介護や医療を受けさせるための契約や申請を代わりに行なうことが必要です。そして、介護を受けさせるには現実的にお金もかかるのでお金の工面が必要です。しかし、このお金の工面という点で、実は思わぬ現実が待ち受けています。たとえば、実の息子さんや娘さんが、「認知症の母を施設に入れるのに、母の名義の銀行の預貯金から支出しよう」「父が認知症になり今は施設にいるから、空き家になった実家をこれを機に売却しよう」と銀行や不動産業者に出向いたとしても、「はい、やりますよ」とはなりません。まずは「本人さんでないと手続きできません」と言われますし、「銀行に「本人は認知症だ」と伝えた途端、口座を凍結されてしまった」という話も聞きます。子供さんからすれば、「自分の親のことなのに、どうして実の子の自分ではダメなんだ」と納得できないと感じますし、死活問題になりかねません。銀行や不動産業者は融通がきかない!と言いたくもなりますが、実は銀行や不動産業者も決して嫌がらせをしているわけではなく、必要な措置をとっているのです。いくら実の子供だからといっても、それだけで口座の解約や払い出し、不動産の売却(いわゆる財産の処分)を無限に認めてしまうと、他の親族や推定相続人(その本人が亡くなった場合に相続人になりうる人)とトラブルになることも考えられます。他にも、その処分によって得られた財産の使い込みや横領といった犯罪も起こりえますし、不動産の売却により本人の居住する場所や権利を奪うことになっては、取り返しがつきません。認知症だからこそ、むしろその本人の財産がしっかりと保全するされる必要があるのです。</div><div>ではそうなってしまった時の方法は?そうならないために事前に備える終活は?というと、使える制度の一つとして、後見制度があります。後見についてはこれまでのコラムでもご説明していますので、そちらを参考にしていただければと思います</div><div>「実の親子関係であるというだけでは、認知症の親の財産を処分できないという現実がある」 今回の「終活って何すること? その④」の中で一番お伝えしたいのは、 ここです。「子供と同居しているから、何とかしてくれるだろう」「親の介護?何とかなるだろう」というお話を聞くことがあります。何とかなる、何とかするのが一番ですが、将来のことは誰にも分かりません。歳を重ねれば重ねるほど、「いつかの将来」は確実に「今現在」に近づいていきます。</div><div>この現実をあらかじめ知っておいていただくことで、「では今のうちにやっておくべきことは何か?」につながるのではないか、と考えます。</div><div><br></div><div>4回にわたり、「終活って何すること?」をテーマにお話をさせていただきました。</div><div>まずは正しい知識をもつこと、それが終活を考えるきっかけになり、さらに形にすることで、結果的にご自分の意思とご家族を守ることにつながります。</div><div>正しい情報を正しく知るためにも、ぜひ私達専門家をご活用ください。</div>
-

- 「終活」って何すること? ~その③ ご自分の命の瀬戸際に、どこまでの治療を望まれますか?~
- ※写真と本文の内容は関連ございません。<div><br></div><div>今回は、「終活」って何すること? その③、「命の瀬戸際に受ける医療について」のお話です。</div><div>このテーマは、私が看護職として長年医療機関や高齢者施設で従事してきた中で、「終活の中で最も大切なものではないか」と考えるものです。当HPのコラム「リビングウィル、尊厳死」の中でも、何度か取り上げてまいりましたので、ここでは、「尊厳死」や「延命措置」についての詳細な説明は割愛させていただき、私が実際に経験した出来事をお話したいと思います。</div><div>看護職に就いて間もない頃、当時勤めていた医療機関に当時40代だった方が入院されていました。</div><div>この入院患者様は突然の脳の病に倒れ、一時危険な状態に陥られましたが、懸命な治療を受けられ、一命を取り留められました。しかし、重い後遺症が残り、ご自分で口から食事をとることができず、胃に直接栄養を送る「胃ろう」を造設し、一日に3回の必要な栄養をとられている状態でした。目は開けていて今にもお喋りできそうな表情はされているものの、声を発することはできず、ご自分で寝返りをうつこともできない、寝たきりの全介助のご状態でした。</div><div>この患者様には、70代の親御様がおられ、毎日のようにご夫婦そろってお見舞いに来られていました。「今日もいい顔してるね」「今日は○○(患者様のお名前)の好きな歌手の歌のCD持ってきたよ」「髪を整えようね」と、返事はなくともごく自然に話しかけられる姿に、私自身の両親の姿が重なり、現場で働くプロとして失格かもしれませんが、幾度となく涙がこぼれそうになりました。そんな様子が続いたある日のこと、ちょうどこの日担当だった私がケアに入った際に親御様からこんなことを言われました。「こうやって毎日この子の顔見られるのはうれしいけれど、自分たちも歳をとり、いつまで面倒を見てやれるか分かりません。この状態がいつまで続くのか、不安です。生きててくれるだけでいい、だけど、この子は今苦しんでいるかもしれないですね、そうではないですか?」私は返す言葉がなく、ただ曖昧な笑顔で聞くことしかできませんでした。親御様は私たちがケアに入る度に、「すみません」「ありがとう」と毎回仰ってくださいました。しかし、一般的・世間的に「大人」と言われる年齢にある自分たちの子供が、自ら動くことも話すこともできず、食事や排せつのケアを他の誰かから受けている、その姿を見ることは、辛く悲しいことだったかもしれないと、今更ながら思うのです。そして、「本人もそれを望んでいるのか、本当は苦しく辛いのではないか」と思い悩む気持ちになることもごく自然な感情だと思うのです。</div><div>今、医療を受ける患者の権利を守るべく、様々な提言がされています。自らの権利を知り、選択、判断ができるのであれば、ご自身にとって納得のいく医療を受けることにつながるのではないかと考えます。</div><div>しかし、この患者様のケースのように、ある日突然に命の瀬戸際に立たされ、自身の受ける医療に選択や判断をする余地のない状況に陥る現実があることも確かです。その選択や判断を、本人に代わってご家族が迫られた時、ご家族の心理的・精神的負担はどうしても大きくなります。</div><div><br></div><div>「もしもご自身やご家族が命の瀬戸際に立たされた時、どこまでの、どんな治療を望まれますか?」<br></div><div>リビングウィルや尊厳死をテーマとしたお話をさせていただくとき、私はまずこの質問をさせていただきます。「返事に困る」「すぐ答えられない」「考えたくない」などのお答えがほとんどですが、お話の終了後には、「考えなきゃいかんね」「ちょっと家族とも話してみるわ」と仰ってくださる方も多くいます。</div><div>命の重さ、尊さが分かるからこそ、 すぐに答えが出せるものではない質問です。(質問をさせていただく側としても、とても緊張します) しかし、万が一の備え、「終活」の一つとして、ぜひ思いを馳せていただきたいと思います。</div><div><br></div><div>次回は「終活」って何すること? の最終話、~その④ 実はこんな現実が。介護が必要な状態になった時に備える~がテーマです。 </div>
-

- 「終活」って何すること? ~その② ご自分の葬儀に希望はありますか?~
- ※写真は、本文の内容とは関連ございません。<div><br></div><div>今回は、私がご紹介したい「4つの終活」のうちの2つ目のお話です。</div><div><br></div><div>前回は、ご自分の亡き後の相続手続きのお話でしたが、私の経験上、故人様亡き直後に相続人の間ですぐに「相続の具体的な話」が出ることはあまりないように感じます。というのも、人が亡くなると、まずは「葬儀はどうするのか」という話になり、葬儀が終わってからは、関係機関に故人様死亡の事実を伝え、各種手続きをする必要があるからです。</div><div>病院や施設で亡くなった場合、ご家族の心情に配慮しながらもできるだけ早いご遺体の引き受けをお願いされますし、ご家族のもとに戻られたご遺体を次に安置する場所の手配が必要です。その後は一般的に通夜、葬儀、火葬と続き、初七日や49日法要など、それと並行して、関係機関の手続きと、ご家族にとっては体力も気力も必要な出来事が一気に押し寄せます。ですので、相続手続きの前に、こういった「亡き後の手続きに関する事務」を先に行う必要が出てきます。(以下、ここでは死後事務手続きといいます)</div><div>死後事務手続きは大きく3つに分けられます。</div><div>1つ目は、「葬儀に関すること」具体的には、ご遺体の引き受け、搬送、安置(仮安置も含む)、亡くなったことを親族や関係者に連絡する。葬儀や火葬の手配、費用のお支払い。</div><div>2つ目は、「お墓に関すること」具体的には、遺骨の引き受け、搬送、安置(仮安置も含む)、納骨や法要の手配、費用のお支払い。</div><div>3つ目は、「行政手続き、その他」具体的には、市区町村での手続き、年金手続き、ライフラインの停止や支払いの変更、病院や施設の諸費用のお支払い、家具や遺品の処分等。</div><div>当然ですが、故人様はすでに亡くなられているので、ご自身の死後事務を自分で行うことはできません。親族や家族が担うことになりますが、故人様が生前に「自身の死後事務に対しての備え」をしておくと、担う側にとって大変スムーズなことが出てきます。</div><div>たとえば、葬儀について。冠婚葬祭会社さんの互助会に入会し、葬儀や法要のプランについて希望を伝えておく、積み立てをして葬儀代を確保しておく、遺影となる写真を撮影しておく、自分が亡くなった時に連絡してほしい、伝えてほしい人をリスト化しておく、菩提寺があれば亡き後の連絡方法や葬儀や法要について確認しておく、など。</div><div>次に、お墓(納骨)について。遺骨ついての希望、納骨方法やお墓の継承(状況によって墓じまいの検討)、菩提寺との関係についての希望、など。</div><div>最後に、行政手続き、その他について。返却の必要な書類(健康保険証、介護保険証、障害福祉に関する手帳、各種助成関係など)の保管場所を分かるようにしておく、亡き後に相続人が支給が受けられるものについて調べておく(生命保険や年金など)、ライフラインの会社や引き落としの口座がどれかを分かるようにしておく、など。</div><div>実際に死後事務を担った方のお話を伺うと、「葬儀の際にどのような葬儀の形態にするか値段の相場も分からないし、予算も含めて、選択が難しかった」「亡くなったことをどこまでの関係性があった方に連絡したらいいのか迷った」「手続きをしようにも必要な書類などが見つからなくて困った」など大小様々な葛藤や問題を経験されたという方も多くいらっしゃいます。大切なご家族が亡くなる、という出来事は非日常であり、精神的・心理的な負担がある上に、次々とやらなければならないこと、選択しなければならないことが押し寄せ、「悲しんでいる時間もないほどだった」というお言葉も聞かれます。そんな中で、故人様が生前に自分の死後事務について、ご家族に希望をお伝えしたり、具体的な選択や手続きを済ませていただくことによって、残されたご家族の負担は少なからず軽減されると考えます。</div><div>ご自身の「死後事務」について、担ってくれるご家族やご親族がいないケースの場合、専門家などと「死後事務委任契約」を結ぶことによって必要な事務をお願いすることも可能です。担ってくださるご家族やご親族がいる方の場合、「エンディングノート」を使って、希望を伝えたり、必要なものの在処や連絡先等を記しておくことができます。</div><div><br></div><div>「終活」というと「遺言」が代表格と言われますが、人が亡くなると葬儀や火葬、納骨など、ご家族やご親族にとってはすぐにやるべきこと、やらなければならないことがあります。葬儀をはじめ死後事務は、故人様とのお別れに対するお気持ちの部分でも大切な役割があります。ご自身の人生の幕をどのように閉じたいか、まずはイメージしてみるところからはじめてみませんか。</div><div><br></div><div>次回は3つ目、「命の最期に受ける医療について」のお話になります。</div>
-

- 「終活」って何をすること? ~その① ご自分の相続手続きに備える~
- <div>※写真の内容は本文とは関連ございません。</div><div><br></div>突然ですが、「終活」というと、何をどうする、というイメージがありますか?<div>最近では「終活」という言葉も聞き慣れた言葉になってきました。私は終活に関する座談会や講座をやらせていただく際に実際に「あなたにとって「終活」というと何をするイメージですか」と何人かの方にお聞きします。</div><div>「生きているうちに断捨離(身の回りの整頓など)をすること!」「自分のお葬式の予約をしておくこと!」などなど、それぞれの「終活」を教えてくださいます。</div><div>私見ですが、終活というと、「自分が死んだあとに家族が困らないように何かしらをしておくこと」というイメージをお持ちの方が多いように感じます。もちろん、これも必要な「終活」に当たると思います。しかし、終活というのは段階を踏んだ様々な「備え」を指します。特に私がご紹介したい「終活」には4段階あります。</div><div><br></div><div>分かりやすく説明するために、時間を逆にしてご説明していきます。今回は1つ目のご紹介です。</div><div><br></div><div>1つ目は、「ご自分の亡き後の相続手続き」に対する備えです。</div><div><br></div><div>人が亡くなると、その瞬間に「相続」が発生します。相続というのは、故人様の残された財産(プラス、マイナス、全ての財産を指します(遺産))のうち、相続人間の話し合いにより、誰が、何を、引き継ぐのか、次の持ち主を決めることです。これは「遺産分割協議」と呼ばれるものですが、この遺産分割協議には実は隠れた高いハードルもあります。まずは、「相続人全員での協議」が必要になること。相続人が欠け状態で行われた遺産分割協議は無効になるため、まずは相続人が誰にあたるのか調べる必要があります。普段から家族・親族間で連絡を取り合うような関係であればさほど難しいことではありませんが、連絡のとれない相続人がいたり、家族・親族間が不仲である、故人様に前婚歴がありお子様がいらっしゃる、となると、この相続人を特定する調査、作業は困難なものになります。「そもそも相続人ってどうやって調べるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、故人様の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本で婚姻歴や縁組歴等を調べ、法定相続人にあたる方の有無、居所などを調べていきます。その方に婚姻歴がなく、お子様もいないとなると相続順位、相続関係が複雑になり、相続人の特定作業はとても時間も手間もかかってきます。そしてもう一つ、この相続人の中に、「意思能力・判断能力がない方、ないとされる方」がいる場合も、遺産分割協議は無効になります。そもそも遺産分割協議は「自分の意思や希望を他の相続人に伝えたり、他の相続人の意思や希望を聞いたりして、遺産について話し合うこと」ですので、そこには自分が相続人であり協議をするという自覚であったり、最終的に協議がまとまった場合は、協議書に署名・捺印も必要になります。</div><div>ですので、たとえば頭の不自由(主に認知症)があり意思能力・判断能力ない状態の方や、法律上そのように定義されている未成年者等は、遺産分割協議には参加できず、法的な代理人を立てる必要が出てきます。</div><div>高いハードルの2つ目は、財産の内容が明らかでない場合です。先ほども述べましたが、故人様の遺産は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。マイナス、つまり事情があって生前にどなたかからお金を借りていて返済が終わっていないケースや、車や家をローンで購入し、月々返済しているケース、などですが、一番心配されるのが、ご家族が知らないところで故人様がマイナスの財産を持っていた、作っていた、というケースです。家族がそれを把握できないまま遺産分割協議・相続手続きを済ませたはいいが、すでに相続放棄ができなくなってから故人様に多額の負債があったことが発覚した、となると、相続人が不測の負債を抱えてしまうことになってしまうこともあります。</div><div>以上の高いハードルのために、相続手続きが進まず、故人様の残された財産の次の持ち主が決まらない、となると、様々な都合の悪いことが出てきますし、時間の経過は、財産の価値の変化、相続関係の新たな変化までもたらす可能性もあります。また、遺産を巡って、家族・親族関係がこじれ泥沼化することで「相続」は「争族・争続」とも呼ばれます。</div><div><br></div><div>さて、話の冒頭に戻りますが、ではご自分の亡き後の相続手続で、家族・親族間の無用な争いごとを防ぎ、また何よりも、ご自分の残した財産をご自分の託したい方に託すことができる備え、「終活」の一つが、「遺言を残す」ことです。</div><div>遺言の種類や作成時の注意点など詳細はここでは触れませんが(コラム「遺言作成」を併せて参考にしていただければ幸いです)、法的に有効な遺言があれば、原則として遺産分割協議を経ることなく、遺言通りに財産の分配がされます。</div><div>相続人全員による話し合いが必要なければ(遺産分割協議が必要なければ)、相続手続きに関して時間や手間は随分省くことができると考えます。</div><div>「遺言」のお話をさせていただくと、「自分には遺言を書くような財産なんてないから」とか、「なんだか堅苦しい」「大変そう」といった感想が聞かれます。しかし、これは終活全般に言えることですが、遺言作成は、ご自分の築いてきた人生や財産と向き合い、次の担い手に託すという大変重要な役割を持っています。ご自分の大切な思い入れのある財産を確実に次世代に繋ぎ、また、残されたご家族の無用な争いごとを避けるためにも、終活の代表格である「遺言作成」をおすすめしたいと思います。</div><div><br></div><div>次回は2つ目、「死後事務委任」についてのお話になります。</div>
-

- 家族を守るためにも
- ※写真と本文の内容とは関係ございません。<div><br></div><div>私はこれまで看護職として働いてきましたが、その中で高齢者施設で働くことが期間としては一番長いものでした。</div><div>さて、これはあくまでも私の経験上のお話で大変恐縮なのですが、それまでの生活スタイル・生活の場から離れ、新しく施設に入所される入所者様のほとんどは、環境の変化やご自分を取り巻く人間関係の変化(同じ入所者様やスタッフなど)にすぐに馴染むことが難しく、何らかの変化や不調を訴えられたり、言動になって表れる方が多くいらっしゃるように感じます。たとえば、毎日あった排便が止まってしまい便秘がちになった、夜眠れない、食欲がわかない、などなど、いわゆる急激な環境の変化が精神的・心理的ストレスになり、身体の不調となって表れる方がとても多いです。また、身体だけではなく、物忘れや時間の感覚のズレ、ご自分のいる場所、入所するまでの経過が分からなくなり、徘徊や昼夜逆転、抑うつや怒りっぽくなる、など、一時的なものもありますが、頭の不自由、いわゆる認知症様の症状が見られるようになる方もいらっしゃいます。</div><div>施設によるとは思いますが、私が今までにスタッフとしてお世話になったところでは、新規の入所者様のご家族やご関係者に、「入所して1~2か月は急激な体調の変化も十分に起こりえます」とご説明していました。実際に入所してから数日や数週間で脳血管疾患、心血管疾患を起こし、救急搬送や緊急入院に至る方も珍しくありません。とくにこれらの疾患の場合、急激に命の危機に瀕した状態に陥ることが多く、医師から、「どこまでの治療を求めますか」とご家族に説明がされるケースにも何度か立ち会いました。</div><div>ご家族としては、施設が決まり手続きなどを経て荷物の搬入なども終わり、これでご本人の身の安全や生活の場は確保できた、そして自分たちも少し落ち着けるだろう、と思っていた矢先に、そのご本人の容態が急変し、命の瀬戸際に立たされている…この厳しい現実をすぐに受け入れることは到底難しいのではないでしょうか。さらにその上に、どこまでの治療をするか、いわゆる、延命措置と呼ばれる措置を行うかどうか、これを決めてくださいと言われたとすると、かなりの心理的ご負担が生じることになります。ご家族がその時に延命措置をすると決めたとして、しないと決めたとしても、その後にご本人にとってこれで良かったのかと長く思い悩まれる姿もまた多く見てきました。「(入所の時に)こういうこともあり得ると聞いていたのに…その時は深く考えていなかったんですよね、まさか現実になるなんて…」と苦しい胸の内を打ち明けてくださるご家族もいらっしゃいました。</div><div>想像してみていただきたいと思います。</div><div>もしこんな「まさか」の事態に備えて、ご本人自身が、「自分の命の瀬戸際にどこまでのどんな治療を望むのか」をきちんと意思表示し、ご家族にあらかじめ伝えられていたとしたらどうでしょうか。延命措置を受けるか受けないかというような場合、ほとんどのケースで、すでにご本人が自身ではどうしたいと意思表示ができないような状況・状態におかれていることがほとんどだと思います。そんなご本人からすでに先に、「自分が万が一そんな状態になったら)ああしたい」「こうしたい」「ああしてほしい」「こうしてほしい」と聞けていたのであれば、ご家族は「本人の望んでいた通りにしてあげよう」と思えるのではないでしょうか。またそう思えることで、ご家族自身も究極の選択や判断を自ら迫れることなく行うことができ、心理的ご負担が少しでも軽くなるのではないでしょうか。</div><div>「延命措置」と言われても、どことなく自分事としてはイメージできない、したくない、という方も多いのではないでしょうか。 しかし、人がいつ命の終わりを迎えるか、誰にも分からないことです。年齢に関係なく、不慮の事故などで本当にある日突然に命の瀬戸際に立たされることも考えられます。そういった中で私たちは生活しています。<br></div><div>「自分らしく最期を迎える」ためにも、命の瀬戸際に立たされた場合に、どこまでのどんな治療を望むのか、ぜひイメージしてみる機会、きっかけを作ってみてください。</div><div>子供が結婚した、孫が生まれた、大切な方が亡くなった、などなどの人生における折に触れて「自分事」として考えてみてください。</div><div>イメージは、意思や望みを生み出します。意思や望みがあるとしたならば、声に出して大切な方に伝えてみてください、そしてできる限り形にしてください。これは今回のような命の瀬戸際における医療のみならず、全ての「終活」のスタートになると私は考えています。</div><div><br></div><div>皆様の「イメージ」と「意思表示」は、いつか来るかもしれない万が一の時の備えとなり、大切なご家族を守る道しるべとなります。</div><div>どうか皆様の想いが長く確実に大切な人に伝わりますように。</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>
-

- 不動産相続登記義務化に伴って。
- <div>※写真は本文の内容とは関連ございません。</div><div><br></div>私の両親は70代後半。まだまだ元気でいてくれるのですが、私が終活を専門としていることもあり、無言(または有言?)の圧力からか、最近は自分たちの将来について考えることが増えたようです。<div>先日のこと。父から父の所有している土地について、本当に自分の名義になっているか心配だと相談がありました。</div><div>父は男3人兄弟で、父の父(以下、祖父)に相続が発生したのを機に、土地を相続しています。ただ、父は次男ということもあり、祖父と同居していた長男夫婦が相続に関する手続きはきっとしてくれたのだろうが、昔のことで覚えていない、とのこと。今年度から不動産の相続登記が義務化されたとのニュースを見て、今耕作している畑が、間違いなく自分のものになっているのか不安になったようです。私は父からの相談を受け、早速法務局の支局で、父の不動産について全部事項証明(不動産登記簿謄本)を取得しました。父の心配は杞憂に終わり、祖父が亡くなった以来自分のものとして使用、管理してきた土地は全て父の名義になっていました。念のため、自宅の宅地と建物についても調べましたが、しっかりと父名義でした。父はもちろんですが、母も私も一安心しました。</div><div>父と話をして感じたのは、父の世代には、「長男が家督を継ぐものであり、親の残した財産は長男が相続するもの」という考え方が少なくともどこかしらにあったのではないか、ということです。特に父の生まれ育った地域は田園風景広がるのどかなところ。今では時代の変化とともに少しずつ変わってきましたが、町内や地区の行事、風習、慣習など古くからのしきたりのようなものが根付いています。そんな中で、個々人や親族内における先祖代々のならわしも然りなのではないでしょうか。この目まぐるしく変わる世の中において、20年前、30年前と今とでは、確実に様々なことが変わってきています。少子化に伴う核家族化、医療の発展に伴う平均寿命の延びなどは、故人様亡き後の相続とも密接に関わってくるのではないかと考えます。</div><div>少し話はズレましたが、とりあえず、父の不安の一つだった不動産の登記と所有については、今のところ名目ともに大丈夫ということが分かりました。</div><div>先ほども書いたように、今年度から不動産相続登記が義務化されたことに伴い、「何年か前に相続したはずの土地が自分の名義になっているかがはっきりしない」というご相談をいただくようになりました。</div><div>このような場合には、ぜひ該当不動産の全部事項証明を取得してみてください。不動産の所在や権利関係(所有者や抵当権の有無など)が記載されていますので、ご自分の名義になっているか調べることができます。全部事項証明は、お近くの法務局の窓口で取得することができます(不動産所在地の管轄の法務局以外でも可能です)また、法務局ホームページよりオンライン申請も可能です。また、この全部事項証明はその不動産に権利関係のない第三者でも取得することがきます。</div><div>登記に関する業務は司法書士の業務となり、行政書士が登記申請書類等を作成したり代理で申請することはできません。しかし、行政書士は連携する司法書士をご紹介したりなど、調査や手続きをよりスムーズに行うための橋渡しをすることができます。ぜひお役立てください。</div>
-
- 大切な人の、「その先」を想う
- <div>※写真の内容は本文とは関連しておりません</div><div><br></div>私が個人的にお世話になっている、今は施設に入所されている方がいます。ご高齢ですが、頭や体の不自由もなくまだまだお元気な方ですが、施設入所当時から、今は空き家になっているご自分のご自宅をずっと気にされていました。<div>元々大きなお屋敷で、配偶者様に先立たれ、お子様方も結婚し遠方に住み、長年おひとり暮らしをされていましたが、年もとったし、最近は物騒だから…と自ら施設を探し、現在にいたっています。</div><div>最近この方から、自宅の建物を取り壊し、更地にして、売りに出すよう、お付き合いのある不動産屋さんに頼んだとお話をうかがいました。もうこの先誰も住む予定がないから、とのこと、そして、庭木の手入れや、傷んだ建物の修繕、警備会社を入れての防犯など、空き家を維持するにも大変な費用がかかっているというお話でした。</div><div>その方がまだご自宅での生活をされていた頃を知っているので、私は少ししんみりしました。「慣れ親しんだおうちがなくなるのは寂しいね」そう声をかけると、その方は、「そうだね、でも、このままにしておいても、子供たちが困るでしょう? 自分が死んだあとに、子供たちに、「壊すのはしのびない」「申し訳ない」と思ってほしくないから」と、きっぱり。その表情に全くの寂しさはないとは感じませんでしたが、どこか、スッキリした表情で、穏やかな笑顔でした。</div><div>私は、この方のお子様方に近い年齢なので、この言葉が、とても心に響きました。</div><div>この空き家の登記簿上の所有者であるこの方に相続が開始した場合、相続人であるお子様方が相続することになります。この4月からは不動産相続登記が義務化されたため、必ず次の所有者を決める必要が出てきます。そうすると、相続して登記の名義変更までしたはいいけれど、住むこともないのに、この空き家の維持管理を継続して行わなければなりません。ましてやお子様方は、遠方にお住まいなので、維持管理がさらに困難なものになることは容易に想像できます。</div><div>この方は、ご自分の亡き後に、お子様方にこういった負担をかけたくないと、今回処分することを決めました。</div><div>さらに、実質的な負担だけではなく、「申し訳ない、しのびないと思わせたくない」とお気持ちの面での負担までも考慮されたのです。「子供たちには今の生活を安心して送ってほしいから」と、最後におっしゃいました。</div><div>お子様方も、最初はびっくりされていたものの、この方の強い意志を知って、承諾されたそうです。</div><div>今回のお話をうかがい、この方の選択や判断がどうか、ということではなく、この方が、大切なお子様方の「その先」を想って行動をされたんだということに、私はとても胸が熱くなりました。人は年齢を重ねるとともに、体力や気力の衰えを感じ、将来に対する不安も増していくものだと思います。この方もきっと例外ではない中で、ご自分とお子様の将来を想像し、最善だと思う方法を選ばれたのでしょう。人生の大先輩の大きな出来事をお聞かせいただき、私はとても光栄に思いました。</div><div>「終活」は、ご自身の納得、安心の将来や最期に備えるためのものです。しかし、側面の一つとして、「残されるご家族のため」でもあると私は考えます。大切なご家族の「その先」に寄り添った終活は、間違いなく残される側の道しるべになるのではないかと思います。</div>
-
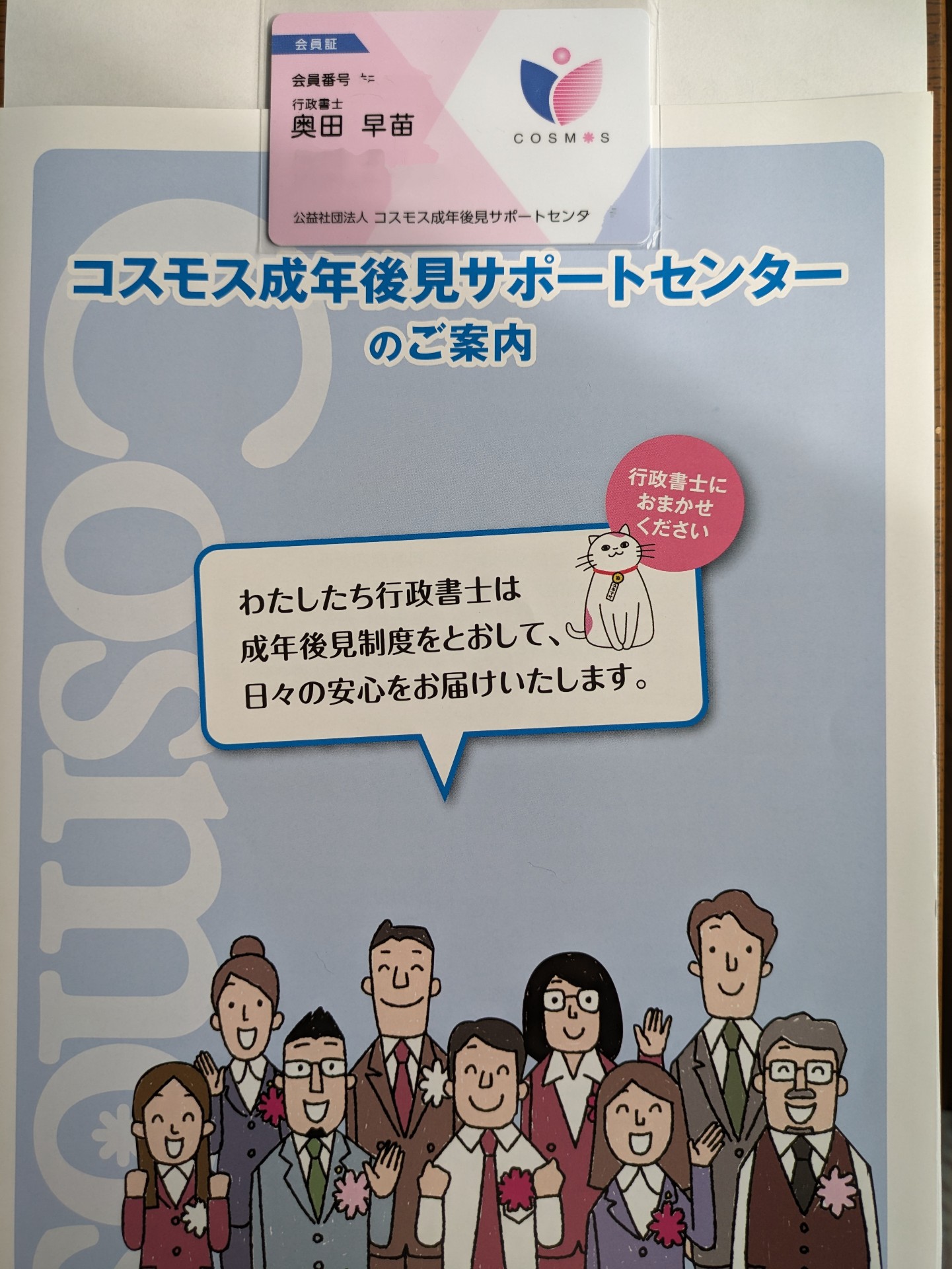
- ~介護が必要な状態になってから、に備える~ Part ③
- 前2回に続き、「介護が必要な状態になってから、に備える」<div>3回目、最終回の今日は、「任意後見契約」をテーマに書かせていただきます。</div> <div><br></div><div>2回目でお話した「法定後見」は、ご本人に「頭の不自由」が起こってからその財産や権利を守るために申立てすることができる制度となっていることをご説明しました。</div><div>では、ご本人の判断能力が残っているうちに、ご本人の意思で、「将来の財産や権利を誰かに託す」ことができる制度はあるでしょうか。ご紹介したいのが、「任意後見契約」です。</div><div>同じ「後見」でも、この任意後見契約制度は、法定後見制度とは仕組みが異なるものになります。</div><div>一番の大きな違いは、「契約」であるということです。契約、つまり、当事者の間で、「この人と結びたい」という双方の意思表示の合致があれば結ぶことができます。この「任意後見契約」に関しては、たとえばAさんが、「もしも将来万が一、自分に頭の不自由が起こったら、Bさんに面倒をみてもらいたい」という気持ちがあり、Bさんにも、「Aさんに将来万が一があったら、私が面倒を見てあげたい」という気持ちがあれば、結ぶことがきでます。</div><div>流れとしては、</div><div>①Aさん(任意後見委任者)とBさん(任意後見受任者)とで、任意後見契約を公証役場で公証人のもと公正証書で締結する </div><div>②Aさんに頭の不自由が起こったら、Bさんが家庭裁判所に後見監督人付与の申し立てをする </div><div>③Bさんは任意後見受任者から後見人になり、後見監督人の監督のもとAさんの後見業務を行う</div><div>この任意後見契約は、同時に「委任契約」も締結しておくことをおすすめします。任意後見契約は、Aさんに頭の不自由が起きてから初めてBさんが申立てをし、後見人としての立場を与えられるものですが、頭の不自由がなくとも、ご年齢とともにAさんに体の不自由が起これば、少なからず何らかのサポートが必要になります。その時、Aさんにはまだ判断能力がある状態なので、Aさんを差し置いてAさんの財産の処分や法律行為までをBさんが行うことはできませんが、たとえば、介護申請や入院や入所の手続き、家賃や光熱費の支払いなどをAさんの代わりにBさんが行うことができるというものです。</div><div>どちらの契約も、AさんがBさんに対し、「私に万が一があったら、Bさんにこういうことをお願いしたい、託したい」という内容を「代理権目録」としてあげておく必要があります。</div><div>この契約の一番のメリットは、「ご本人のお気持ちや意思、タイミングを大切にできる」ことです。たとえば、ご高齢のご本人を案じ、ご家族など身近な方が、「心配だから、財産を預かるよ」と言っても、ご本人は「はい、お願いします」と簡単には言えないことも多いものです。やはり、通帳や印鑑、お財布など大切なものは、できる限りは自分の手元に置いておきたい、自分で管理したいと思うものです。しかし、体の不自由や頭の不自由をきっかけに、または、不自由がなくても、年齢的な衰えから自分で管理することに対し不安や心配を抱えるケースもありえます。「最近うっかり物忘れが多くなって、大切な物の在処を忘れてしまいそうで…」「言葉巧みにものを売りつけられそうになった」など、「これはもう、誰かにお願いしないと危ないな、怖いな」とご自分のタイミング、意思で、信頼できる相手に託すことができるのであれば、ご本人の納得、安心につながるものだと思います。</div><div>また託された側も、「自分はきちんとした契約のもとで動いている」という安心感と責任感をもって、ご本人のために必要なサポートをすることができます。</div><div>他に、法定後見との違いでメリットとして、</div><div>契約なので、報酬については双方の協議の上あらかじめ決めておくことができる(親族間のケースの場合、無報酬とすることがほとんどです)</div><div>段階を踏むことができるので、準備期間を設けやすく、後見人として業務ができるまでの手続きがスムーズになる</div><div>などが挙げられます。</div><div>反対にデメリットとして、</div><div>第三者の目が届きにくい(委任契約のうちは、家庭裁判所も後見監督人も入らないため、ご本人が窃盗や横領などの犯罪に遭うケースが起こりうる)</div><div>実際に頭の不自由が起きても、任意後見受任者が後見監督人の申し立てをしないことで、ご本人の財産や生活が守られにくくなる(後見監督人がつくことへの不信感、申し立ての煩わしさなど)</div><div>などがあげられます。</div><div><br></div><div>近年、核家族化、少子化とともに、身寄りのない高齢者の財産や生活をどう守るかが、社会的課題になっています。</div><div>介護を必要とせずに人生の最期を迎えることは一番の理想であり、どなたもが望むことではあります。</div><div>しかし、もしも将来万が一、介護が必要な状態になったとしたら、誰に何を託したいか、誰に何をお願いしたいか、どんな生活を望むか、そのために、元気な今のうちに何ができるか、どんな備えが必要か、ぜひ「イメージすること」「想像すること」をしてみていただきたいです。</div><div><br></div><div>今回ご紹介した後見に関する制度も、最近では耳にするようになってきましたが、その具体的な仕組みまではまだまだ周知が追い付いていないというのが、私の個人的な感想です。<br></div><div>3回にあたってご説明してきましたが、各制度についてまだまだお話したいことがたくさんあります。</div><div>ぜひこの機会に、「後見」について知っていただけたらと思います。</div><div>また、適切な指導や管理のもと行政書士が後見について承る、「コスモス後見サポートセンター」という組織もございます。コスモスの活動を通して、行政書士の後見に関わることの意義もあわせて知っていただくきっかけにしていただけたらと思います。</div><div><a href="https://www.cosmos-sc.or.jp/">公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター (cosmos-sc.or.jp)</a> ☆ぜひご覧ください☆</div><div><br></div><div><br></div>






