コラム
-
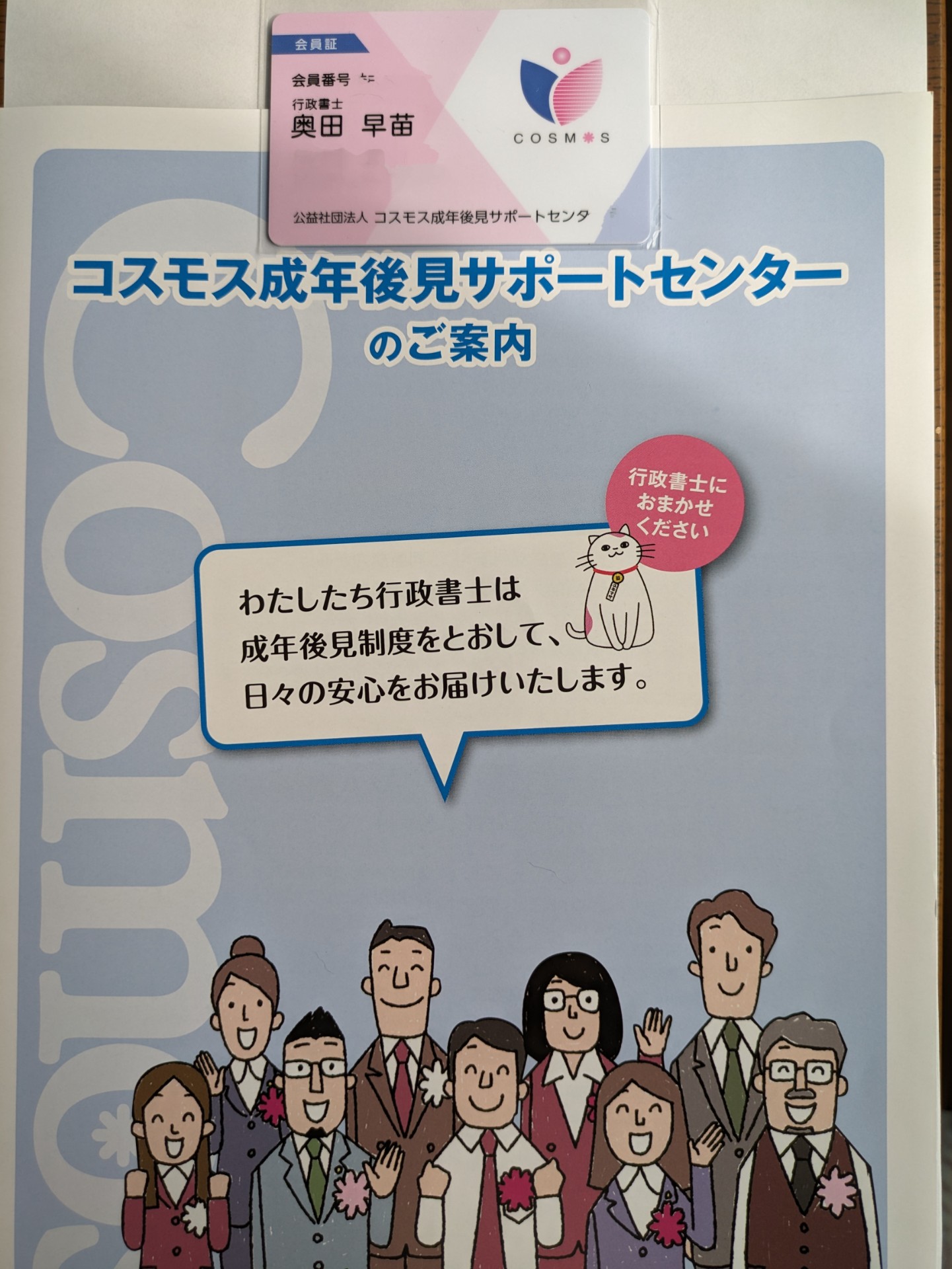
- 後見制度は悪法?
- 先日のこと。普段からお世話になっている介護福祉関係者の方から連絡をいただきました。<div>この方が担当されている利用者様に協力していただける親族がおらず、後見人をつけるしかないという話が出ているが、「後見って悪法ですよね、だからできたら使いたくないんです」と。</div><div>このようなご相談を受けることは少なくありません。行政書士で組織するコスモスあいちの会員として普段後見業務をやらせていただいている私としては複雑な気持ちにもなりますが、実はこういったご相談は、後見制度を正しく知っていただくチャンスでもあるととらえています。</div><div>話は戻り、この方に「どうして後見は悪法だと思うのですか?」と聞くと、こんなお返事がありました。</div><div>「後見人はお金のことしか考えていないと聞いた」「本人に会いにも来ないと聞いた」「本人が亡くなると本人の財産を全部持っていってしまうと聞いた」などなど…。たしかに、この話だけ聞くと、後見は悪法、後見人は悪人と言われても仕方ないかもしれませんね。ただ、後見人としてきちんと正しくご説明し、誤解を解きたいことも多くあります。</div><div>・「後見人はお金のことしか考えていない」→後見人は本人の財産をお預かりし、本人の命や生活、人生を守るためにお預かりした財産を維持・管理・処分していきます。<br></div><div>・「本人に会いにも来ない」→少なくとも私や私の知っている後見人は、定期的に本人を訪問、面談し、衣食住に困っていないか、虐待等を受けていないか等の確認を身上監護の一環としておこない、また、関係者との連携を図っています。</div><div>・「本人が亡くなると後見人が財産を持っていく」→本人が亡くなったと同時に後見人は辞任となり、お預かりしていた財産は本人の相続人がいればその相続人に引き渡します。</div><div>いかがでしょうか、明確に誤解されているものもありますが、聞き方やとらえ方によっては確かにそう思われても仕方ないかもしれないというところもあります。</div><div>情報社会となった今、ワンクリック、ワンタップで得られる情報は無限にあり、私達の生活を豊かにしてくれるものもたくさんありますが、反対に正しい情報と誤った情報とを見分けるのがとても困難になっていると感じます。この方の場合も、ご自身はまだ後見人が就いている方を担当したことがないとのことで、後見について色々調べてみたけれど、どれも批判的な情報ばかりだったからとのことでした。そして私が一通りご説明したことに対し、「知っておくことも必要だけど、正しく知らなければ、せっかくある選択肢を自ら潰してしまうことにもなるんですね」と仰っていただくことができました。私にとっても、この方が、目先の情報だけにとらわれず、声をあげて質問してくださったことは意義のあることだったと感じております。</div><div>超高齢社会において、高齢者を支援するにはチーム一丸となることが必要だと思います。そして後見人もそのチームの一員として、本人に代わって法律行為を通し財産管理や身上監護をしてまいります。ぜひ後見人を身近に感じていただき、そのチームに入れていただきたいと思います。</div>
-

- 人生の大先輩から学ぶこと
- <div>(※写真と本文の内容とは関連ございません)</div><div><br></div>つい先日のこと。認知症症状のあるA子さんと並んでテレビでニュースを見る時間がありました。<div>今、ニュースで報道されない日はないのではないかというほど深刻な社会問題になっている特殊詐欺。A子さんと見ていたニュースでも、特殊詐欺により多額の預貯金を騙し取られた高齢の男性の被害の実態が流れました。手口は本当に悪質かつ巧妙。被害に遭われたご本人の心情を思うと、心底怒りがわいてきます。「他人様のことをどう思っているんだろうね、許せんわ!」と思わずつぶやく私。隣のA子さんには伝わらないだろうなあと思っていると、なんとそのA子さん、私のつぶやきに続いてこんなことを仰ったのです。</div><div>「こーんなくだらんことに頭使うくらいなら、もっと世のため人のためになることに頭使わなかんわ!とろくさい!!」 (とろくさい、というのは尾張弁なのでしょうか、ばかばかしい、呆れてものが言えない、というニュアンスで使っています) </div><div><div>そう、A子さんは、特殊詐欺の犯人にモノ申しているのです。人を騙してお金を搾取する方法を考える知恵があるのであれば、もっと良いことにその頭を使え、世のため人のために知恵を絞れ、と。</div><div>実はA子さんは元々、こちらから問いかけや声掛けをすればお返事をするという控えめな方。ご自分から声をあげたり、感情を出されるような方ではありません。しかし、この時は違いました。隣で聞いた私は目が点…A子さんの方を見ると、その目は真剣、怒りの表情。認知症であることなどすっかり忘れてしまいそうな勢いです。 </div><div>私はA子さんの言葉に感心すると同時に恥ずかしさと申し訳なさでいっぱいになりました。A子さんは認知症だから伝わらないだろうと勝手に決めつけていたからです。でも実際のA子さんは違いました。どこまでこのニュースの実態をご理解されたのかは分かりませんが、少なくとも「人を騙すこと」は悪いことで決してやってはいけない、騙す知恵があるのであれば人の役に立つことに使え、と仰ったのです。</div><div>長年看護職としてご高齢の方に接する機会をいただいてきましたが、その中で認知症と診断された方でも、相手の表情やしぐさを読み取る、感じ取るというところでは、こちらが驚くほど敏感で繊細な感性を保たれる方は多いと感じます。ケア中にふと考えごとをしてぼんやりしていると、「あんた、頑張りすぎちゃいかんよ!」と肩をもんでくださったり、マスク越しに小さくため息をつくと、「迷惑かけてごめんね」と謝られてこらたり。こちらが無意識にとっている行動で心の中を見透かされているように感じます。これはきっと人生において長い長い時間とたくさんの経験を積み重ねられてきたからこそのなせる技、たとえ認知症になったとしても失い切ることのない本能のようなものではないでしょうか。</div><div>仕事と家庭の両立や職場の人間関係で悩んだ時、人生の大先輩方を前にすると、「この方にも同じように悩んだ時があったのかな。それを乗り越えてきたんだな」と思い、「私なんてまだまだヒヨッコ!大丈夫、私にもできる!」と不思議なパワーをもらえる気がします。</div><div>A子さんの言葉に、人生の大先輩から学ぶことはたくさんあるのだとあらためて気づくことができました。</div></div><div>人間、歳をとらない人はいません。しかし、年齢の積み重ねと同時に、様々な出会いや経験も積み重なっていきます。</div><div>まだまだ若輩者の私ですが、いつかは誰かの人生の大先輩として何かを残したり伝えられるような存在になれることを目標にしたいと思います。</div>
-

- 「当事者」になって気付いたこと
- <div>※写真は本文の内容とは関連ございません。</div><div><br></div><div>私事で恐縮ですが、4月にくも膜下出血を発症し、2か月ほど療養期間をいただいておりました。幸いにも発見と治療が早く、現在は後遺症もほぼ消失しスローペースではありますが仕事に復帰しております。治療にあたってくださった主治医の先生と医療従事者の皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。</div><div>決して愉快な話題ではないのですが、ようやく振り返る心の余裕ができましたので、今回の出来事を通して私と私の家族との間で再度考え直すきっかけとなったエピソードを紹介させていただきたいと思います。</div><div>私は3年前に「リビングウィル」を記しました。私は、万が一命の瀬戸際に立たされたとしても、ただ生命を生きながらえさせる目的だけの措置は受けず、時間の経過とともに自然な形で心臓が止まるのを待って死を迎えたいと望んでいるため、それを意思表示したのです。今回医師から病名を告げられた時、意識はしっかりあったものの、看護職の知識と経験から、「私、このまま死ぬかもしれない」と、静かに覚悟を決めました。そして付き添ってくれていた主人にとっさにこう言いました。「もし私に万が一があったら、(リビングウィルを示した)あのカードを先生に見せてね」と。主人は私に動揺を見せまいといつもと変わらない表情で、「分かったから、今は何も心配しなくていいから」とだけ答えてくれました。この後私は入院することになったため、自宅ではしばらく主人と次男の二人となりました。私が入院し主人が帰宅してすぐに、私の記したリビングウィルと、「延命はしない」という希望について、二人で夜中まで話し合ったそうです。私がリビングウィルを記していることは二人とも知っています。その上で、主人は私の意思を尊重してやりたいと次男に話したところ、次男は、「とても受け入れられないから、考え直す時間が欲しい」と訴えたそうです。入院した翌日、次男がお見舞いにきてくれました。病室の扉が開き、私と目が合った途端、次男は泣き出しました。おそらく心配で不安でいっぱいだったのだと思います。(私も母に対してそうですが、自分の母親は不死身、のように感じていたのでしょう。子供から見たお母さんって、いつも元気でチャキチャキしているイメージありますよね、個人的な意見ですが(笑))しばらくして落ち着いた次男からこんなことをお願いされました。「お母さん、お母さんが延命を望まないってことは知ってるんだけどさ…、あれ、ちょっと考えさせてくれないかな」 私は、私の意思であるならば、おそらく家族は反対はしない、従ってくれるだろうと思っていました。次男も私がリビングウィルを記した当時はそう思ったそうです。しかし、主人から私が入院したことや病名、延命は望まないと言っていることなどを聞き、このまま私が死んでしまったらとても受け入れられない、どんな形でもとりあえずは生きていてほしい、生きてそばにいてほしい、と心から思った、と泣きながら伝えてきたのです。これには私も泣きました。たった一晩で次男が私の命についてこんなにも考え、思ってくれたということに、うれしさと申し訳なさといっぱいになりました。同時に、自分の記したリビングウィルは、ひとりよがりの意思表示だったのではないかと深く反省しました。今回のようにその日の朝まで元気だった母親が夜には命の瀬戸際にいる、その状況で、「私は延命措置は希望しないから何もしないで死なせてね」の言葉を聞いていたからといって、「はい、そうしましょう」とはならない、なれない、と。もし私が家族の誰かと反対の立場だったらどうか…と。</div><div>私は終活のご相談を受けた時に、「一番考えていただきたい終活の一つ」として、命の瀬戸際に対する備えについてご説明しています。「命に正解も不正解もない、人によって死生観は違う、今すぐにどうしたいかを決めて形にして残す、ということは難しいこと。でも、だからこそ、折に触れて、「考えること」「想像すること」「声をあげること」をしていただきたい」と。今回の出来事はまさに自分自身に再度この説明を投げかけることとなりました。「私の命は、私が決める」だけではなく、「大切に想ってくれる人がいる私の命だから、じっくり一緒に考えてもらう」ことも必要だと身をもって感じました。</div><div>まさかの病気をし、家族にも心配をかけましたが、自分自身の命と改めて向き合うきっかけを作ってもらったと感じます。一日一日を大切に、そして感謝の気持ちを忘れずに、日々精進してまいります。</div>
-
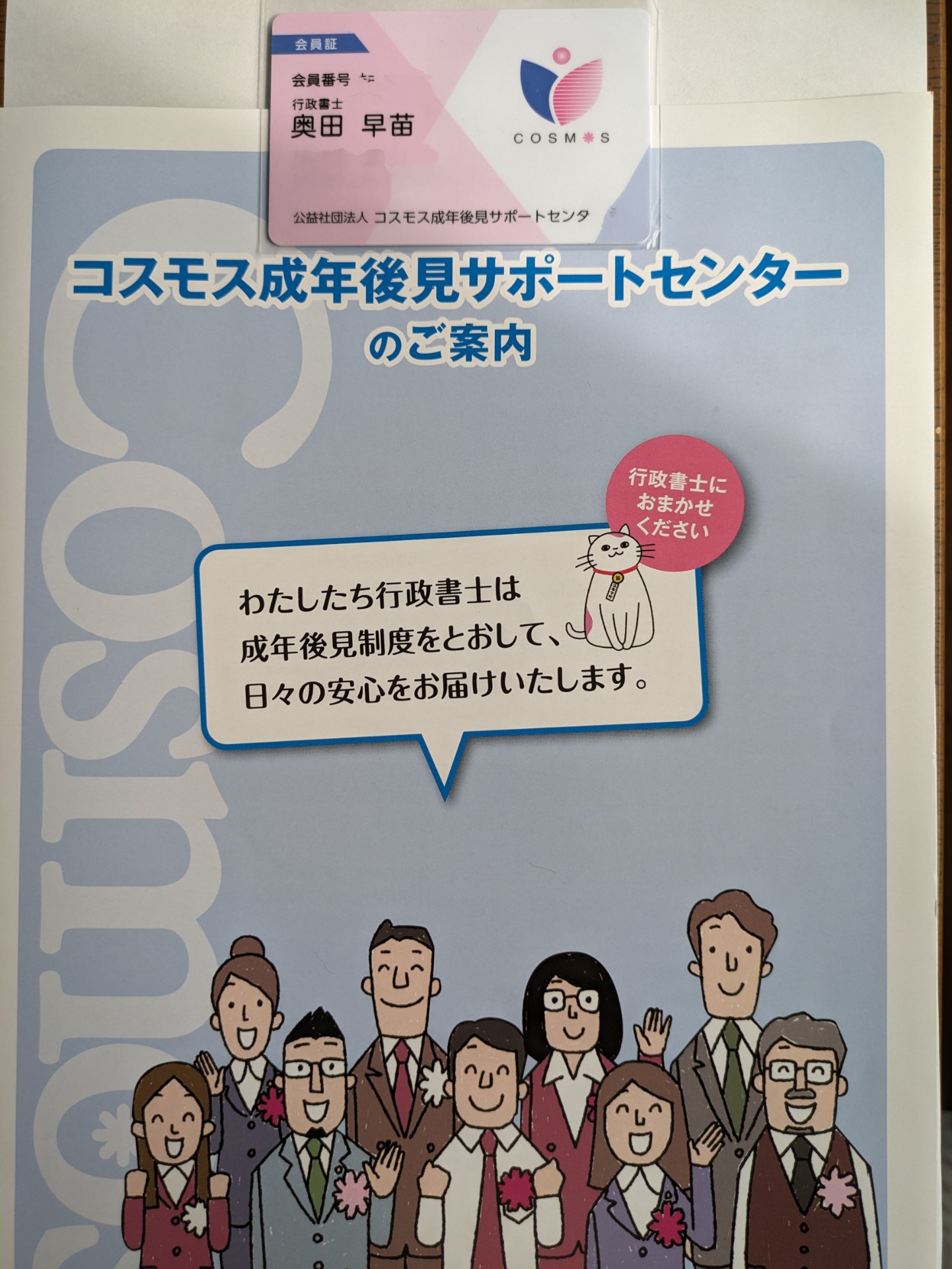
- 「はじめまして、後見人です!」 その⑦(最終章)
- 長丁場でお話してきた「はじめまして、後見人です!」 今回が最終章になります。<div><br><div>終活に関するセミナーや座談会で「後見という言葉を聞いたことありますか」とか「後見制度ってご存知でしょうか」と質問させていただくと、おおよそ出席者の半数以上の方が「聞いたことある」「知っている」と回答されます。その上で「後見に対して、あまり良いイメージがない」「良いことを聞かない」と正直な感想も聞かれます。最近では、SNSの普及等で身近な情報がごく自然に近い形で目や耳に入ってくる機会も増えたと個人的に感じているのですが、「後見」に関する様々なニュースもよく目にします。これも個人的な意見になりますが、どちらかというと、後見に対し否定的な、そして問題視するような記事が多いと感じます。後見人による被後見人の財産の横領等犯罪になりうる出来事は絶対にあってはいけないことですし報道されるべきだと思いますが、たとえば、「後見人が勝手に被後見人の自宅の鍵を変えてしまった」「後見人が勝手に被後見人を施設に入れてしまった」等、被後見人の親族側の主張が記事になっているものも多く目にします。もちろん、この文言を見ると被後見人の親族の方の納得がいかないお気持ちも当然ですし、後見人や後見という制度そのものに対して不信や不満、怒りを覚えるのも当然だと思います。と同時に、この後見人は、被後見人やその親族の方と普段から関係を築けていたのだろうか、とも感じます。私も後見の仕事をしています。若輩者の私が偉そうな言い方をしますが、私が普段から一番気をつけていることは、「情報提供」「情報共有」「報告」「連絡」「相談」です。</div><div>これは被後見人だけではなく、その親族、そして介護福祉医療の関係者、全ての相手方に対して絶対的に必要なことだと考えています。そしてこれは本来、本人に後見の申立てが必要かもしれないと検討を始める時点ですでに行うべきものだと感じます。後見制度の内容や仕組みはもちろん、その上で、ではなぜ本人に後見人をつける必要があるのか、後見人ができること、できないこと、後見人の法的な立場や業務内容等を事前に丁寧に説明することが、後々の後見業務において、後見人自身の身を守ることにもつながります。一度抱かれた不信感は、簡単には払しょくされないですし、この積み重ねが原因で、ゆくゆくは後見人が辞職することになってしまっては本末転倒、結果困るのは被後見人である本人なのです。</div><div>あくまでも推測であり個人的な見解ですが、「自宅の鍵を変えてしまった」のは、被後見人の財産を他者から守るために必要な措置だったかもしれませんし、「施設に入所させてしまった」のは、被後見人の生活や命を守るために必要な措置だったかもしれません。その経緯や理由等がきちんと事前に説明され、後見人として然るべき判断や手続きに基づくものであれば、親族側としてももう少し違ったお気持ちでいられたのではないか、と思うのです。</div><div>私も被後見人を支援する関係者の一人から、「〇〇さん(被後見人)のお金なのに、結局は後見人の価値でしか使えないのですね」と厳しいお言葉をいただいたことがあります。その関係者の方から見て、被後見人の為のいわば必要な経費なのに、なぜ出してあげないのか、本人のお金なのになぜ出し惜しみするのか、と。もちろんその関係者の方に私を責める気持ちがあった訳ではなく、本人の生活をより良くしたい、との一心で思わず出た一言だったと思います。本人の生活をより良くしたい、それは後見人の私も全く同じ気持ちです。ただ、今ある被後見人の財産を、今後いつ終わるか分からない被後見人の人生に備えて、途切れることなく先細ることなく支出していく、これが後見人に任せられた業務である以上簡単に譲れないこともあります。親族や関係者から見れば、時に「嫌われ役」となる覚悟も持たなければと心しております。</div><div>この超高齢社会において、高齢者の方を支援するための方法の一つとして、法定後見制度があります。おひとりさまの高齢者の増加や核家族化等を要因として、法定後見制度のニーズは今後高まっていくのではないかと個人的に考えます。もし皆様の中でご家族や身近な方に後見人がついた場合や、すでに後見人がついている場合には、被後見人を支援する関係者の一人として、ぜひその業務について興味をもっていただき、ご理解・ご協力賜れましたら幸いです。</div><div><br></div><div>全7回を通して「はじめまして、後見人です!」をテーマにお話ししてまいりました。</div><div>法定後見制度は複雑な部分も多く、そしてまだまだ広く知られているとは言い切れない制度だと感じていますが、この記事を通して、皆様にとって後見人の仕事を少しでも身近に感じていただくことができましたら、とてもうれしく光栄です。</div> </div>
-
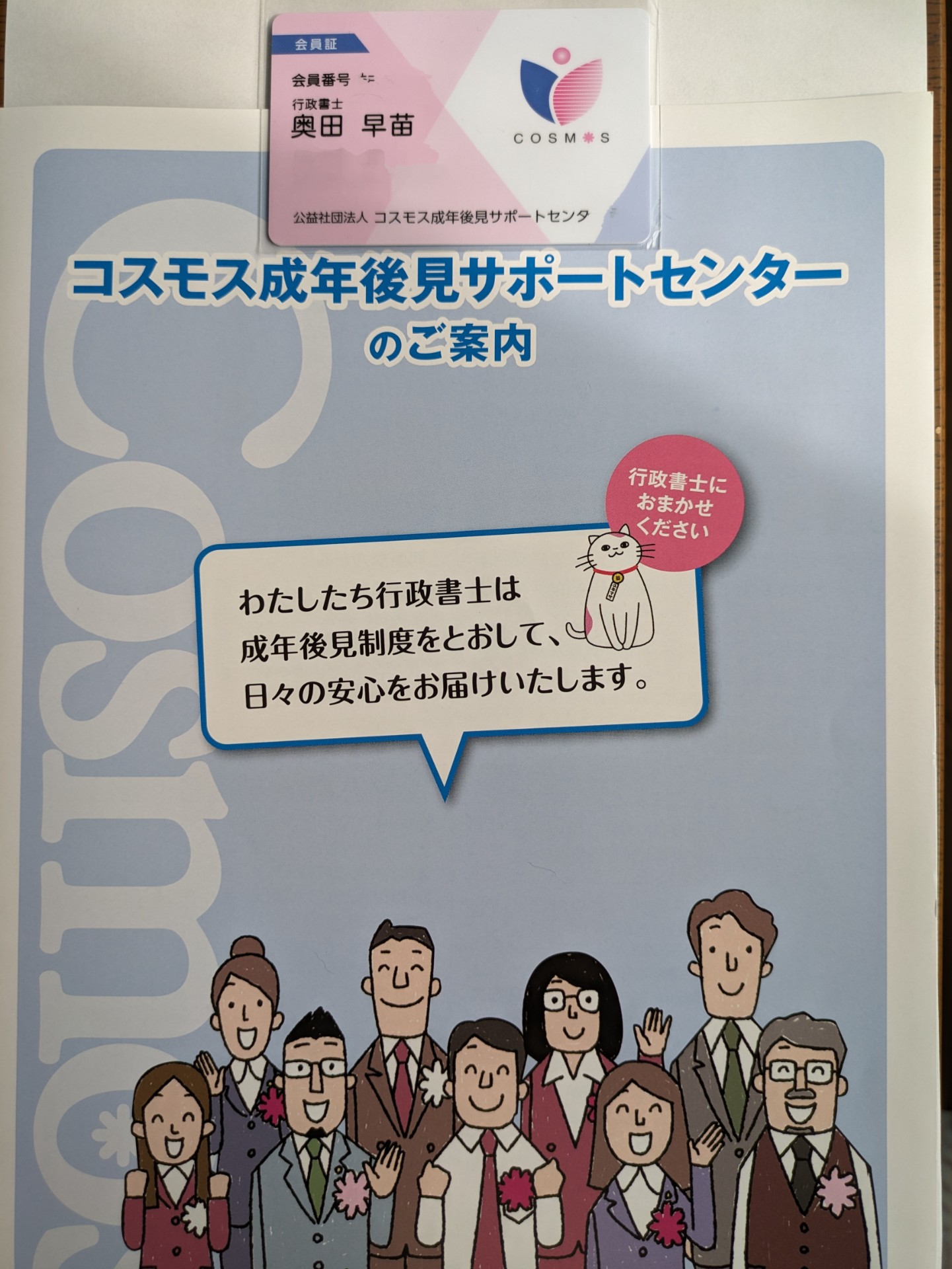
- 「はじめまして、後見人です!」 その⑥
- 「はじめまして、後見人です!」 その⑥<div><br><div>今回は後見人の実際の業務についてのお話です。</div><div>さて、申立てを経て家庭裁判所より後見開始の審判が下りると、後見人に「あなたが後見人に選任されましたよ」という通知、「審判書」が届きます。ただ、この時点ではまだ審判が下りたことのお知らせであり、実際にこの審判が確定するまでには、2週間の不服申し立て期間(即時抗告)が設けられています。この期間内に家庭裁判所より何らかの連絡がなければ「審判確定」となり、後見人はようやく後見業務に着手できます。先にご説明した通り、後見人の業務は、被後見人の「身上監護」と「財産管理」です。意思・判断能力を欠いた被後見人を代理して法律行為を行います。実際の業務として、被後見人の預貯金の管理や、介護や医療サービスを受けるための申し込みや契約、かかる費用の支払いなどが挙げられます。</div><div>後見人の業務はあくまでも法律行為です。したがって被後見人の身の回りのお世話(直接的な介護)等の事実行為や、養子縁組、婚姻や離婚届の提出といった身分行為は行えません。また、実際の後見業務において大きなポイントになるのが、後見人には医療に関する同意権がないということです。具体的には、被後見人の手術等の医療行為への同意はできませんし、延命措置の中止や拒否を選択・判断することもできません。他にも、保証人や身元引受人になることもできませんし、被後見人と後見人との間で利益が相反する行為(たとえば、後見人がお金を借りる際に被後見人名義の不動産を担保にする)も禁止されています。</div><div>こうして挙げてみると、被後見人に対し後見人ができることはごくごく限られているように感じられる方もいらっしゃるのではないかと思います。実際に「後見人がついたところで何をしてもらえるの?」「後見人に何ができるの?」と直球の質問をいただくこともあります。事実行為という面では、被後見人に必要な介護・医療サービスを提供できるようケアマネや福祉関係者に報告・連携・相談し、要介護認定の申請や介護サービスの申し込み、契約、必要な支払いを行う、</div><div>医療に関しては、被後見人の親族と連絡をとり相談する、主治医や医療関係者と連携する、場合によっては身元保証会社の利用を検討し申し込む、等。また、後見人の義務として、家庭裁判所への定期的な報告も行います。原則として年に一度、被後見人の生活の状況や、支出や収入、財産の状況等をまとめ、報告書として提出します。他にも、たとえば大きな財産の処分(不動産の売却等)を検討する際には家庭裁判所に許可を得る必要がありますし、多額の臨時の収入や支出があった場合も連絡する必要があります。</div><div>個人的には、後見人は、被後見人に必要な支援を受けていただくための橋渡しのような立場ではないかと感じています。</div><div>法律上では後見人の業務は大枠として決められていても、被後見人の置かれている状況や環境、送っている生活はそれぞれで、日々の生活時々で起こる課題や問題もそれぞれです。すべてにおいて法律で、「こういう場合はこうしなさい」「ああいう場合はああしなさい」と事細かに決められてはいません。つまり、「何が起こるか分からない」現実に具体的に備える、実際に起こった時に迅速に対処する、そのためにも、被後見人を取り巻く関係者が一丸となる必要があるとつくづく感じております。</div><div><br></div><div>今回は後見人の実際の業務についてのお話でした。次回は「はじめまして、後見人です!その⑦最終章~被後見人をより良く支援するために~まとめ」になります。</div> </div>
-
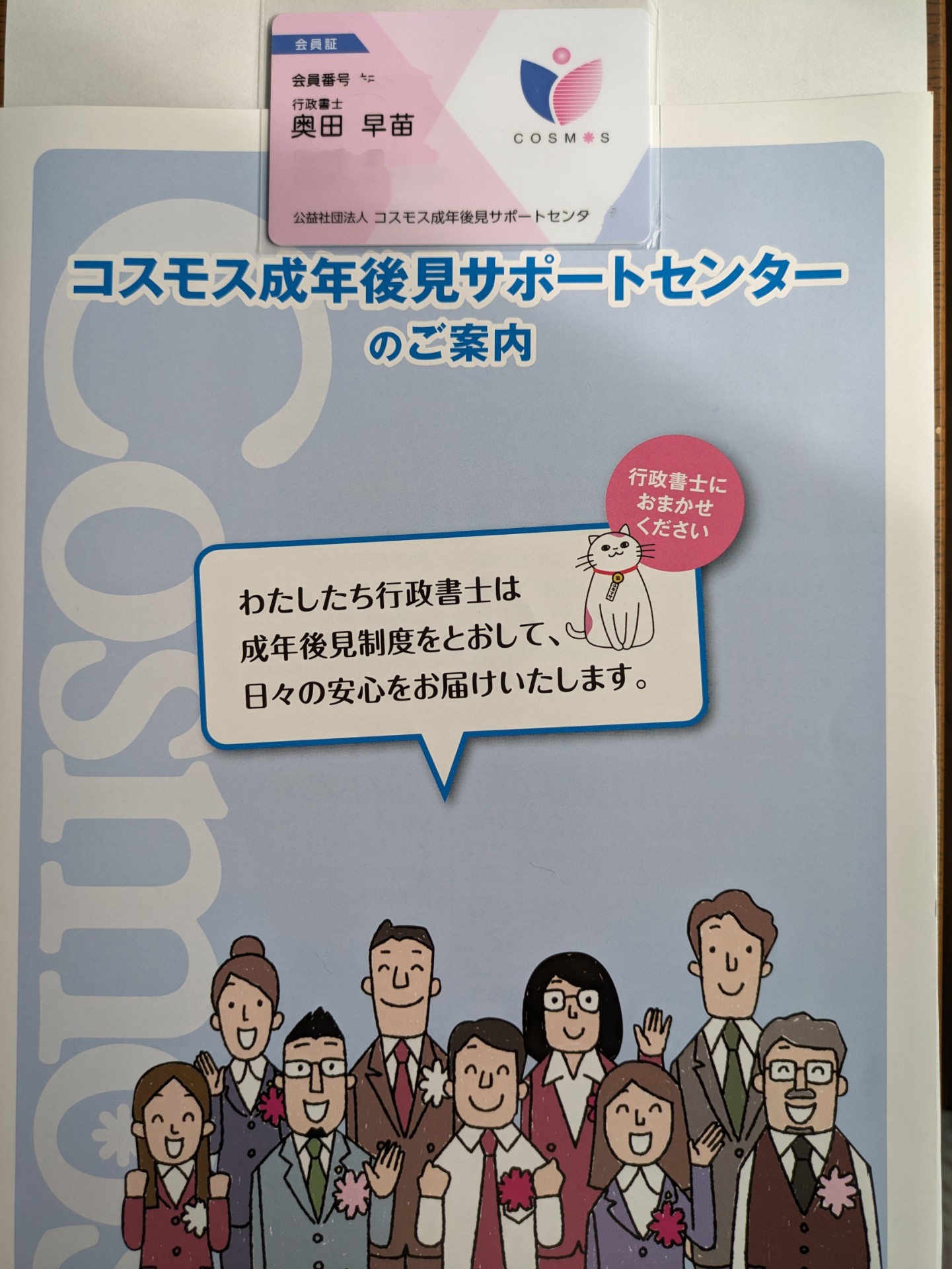
- 「はじめまして、後見人です!」 その⑤
- 今回は、テーマ「はじめまして、後見人です! その⑤ 後見人には誰がなる?」です。<div><br><div>前回までのお話で、申立までの流れや必要事項などをご説明しました。</div><div>それでは実際に「後見人」とよばれる人には誰が選任されるのでしょうか。</div><div>先のお話でも書いた通り、後見人には非常に重要な権限があります。後見人は被後見人(後見を受ける方)に必要なあらゆる法律行為を代理人として行い、また、被後見人が行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為をのぞく)を取り消すことも可能です(民法9条、120条1項)この権限のもとで、意思能力・判断能力を欠く状況にある方の生活や人生(身上監護)、財産(財産管理)を守る必要があります。ですので、後見人は誰でもよいというわけにはいかず、家庭裁判所によって選任されます(民法843条1項)。逆にいえば、「この人に後見人になってほしい」「私が後見人になりたい」と希望し、申立ての際に「候補者」として挙げても、家庭裁判所がその通りに選任しない可能性もあるということです(民法843条4項)。</div><div>実はこの点は、この法定後見制度が使い勝手が良くないと言われる理由の一つになっていると個人的に考えています。のちに被後見人となる方のご親族等からすると、選任された後見人が全く面識のない相手だったとすると、「思いもよらない人に(被後見人の)財産を取り上げられてしまった」「自分たちがいるのに、何もやらせてもらえない」などという不信感を持たれるケースも少なくないのです。特に申立人となった方が、自らを後見人候補者として申立てを行った場合に、自分ではなく全く知らない人が後見人に選任されたとするとどうでしょうか。自分が後見をやれないことに加え、どこの誰だか知らない人に被後見人の財産を預けなければならないとなると、かなりの心理的負担が生じるのではないかと思います。選任された後見人が気に入らないからという理由では、後見の申立てを取り下げることはできません。そもそもご本人(被後見人)が意思能力・判断能力を欠く常況であることを理由に後見人が必要である、と申立てがされているので、家庭裁判所が後見人が必要と判断したのであれば、取り下げはできないのです。</div><div>(ただ、選任された後見人に後見業務において不正行為があった場合等には親族等からの請求や家庭裁判所の職権により後見人が解任される可能性もありますし(民法846条)、後見人側の事由により家庭裁判所の許可を得て自ら辞任することも可能(民法844条)です)後見開始の審判が下ると、基本的には被後見人が亡くなるまでの間、半永久的に後見人が就き続けることになります。つまり、申立のきっかけとなるような出来事がたとえ解決、終了したとしても(たとえば不動産の売却や預貯金の解約等)、後見人による後見業務は継続します。</div><div>私も行政書士で組織するコスモス後見サポートセンターの会員として後見業務にあたっており、案件によっては申立ての段階からご本人やそのご家族、介護福祉関係者の方と接する場面も多いのですが、申立ての際に、候補者として名前を挙げていただくことはできても、実際に選ぶのは家庭裁判所になります、と丁寧にご説明させていただいております。また、実際に選任されたとしても、後見開始の審判が確定がされるまでは、業務を開始できない旨も重ねてご説明しております。</div><div>しかし、「どこの誰が後見人になるか分からない」と聞くと、そもそもこの制度を使うということに消極的になられる方も多い印象です。後見人による被後見人の財産の横領等の不正行為も社会問題として取り上げられることもある中で、後見人と被後見人との間、また、後見人と被後見人を取り巻く関係者の間、で信頼関係を構築していくか、がとても大きな課題になると考えます。</div><div><br></div><div>今回は後見人には誰がなる?のお話でした。次回は後見業務の実際についてのお話になります。</div> </div>
-
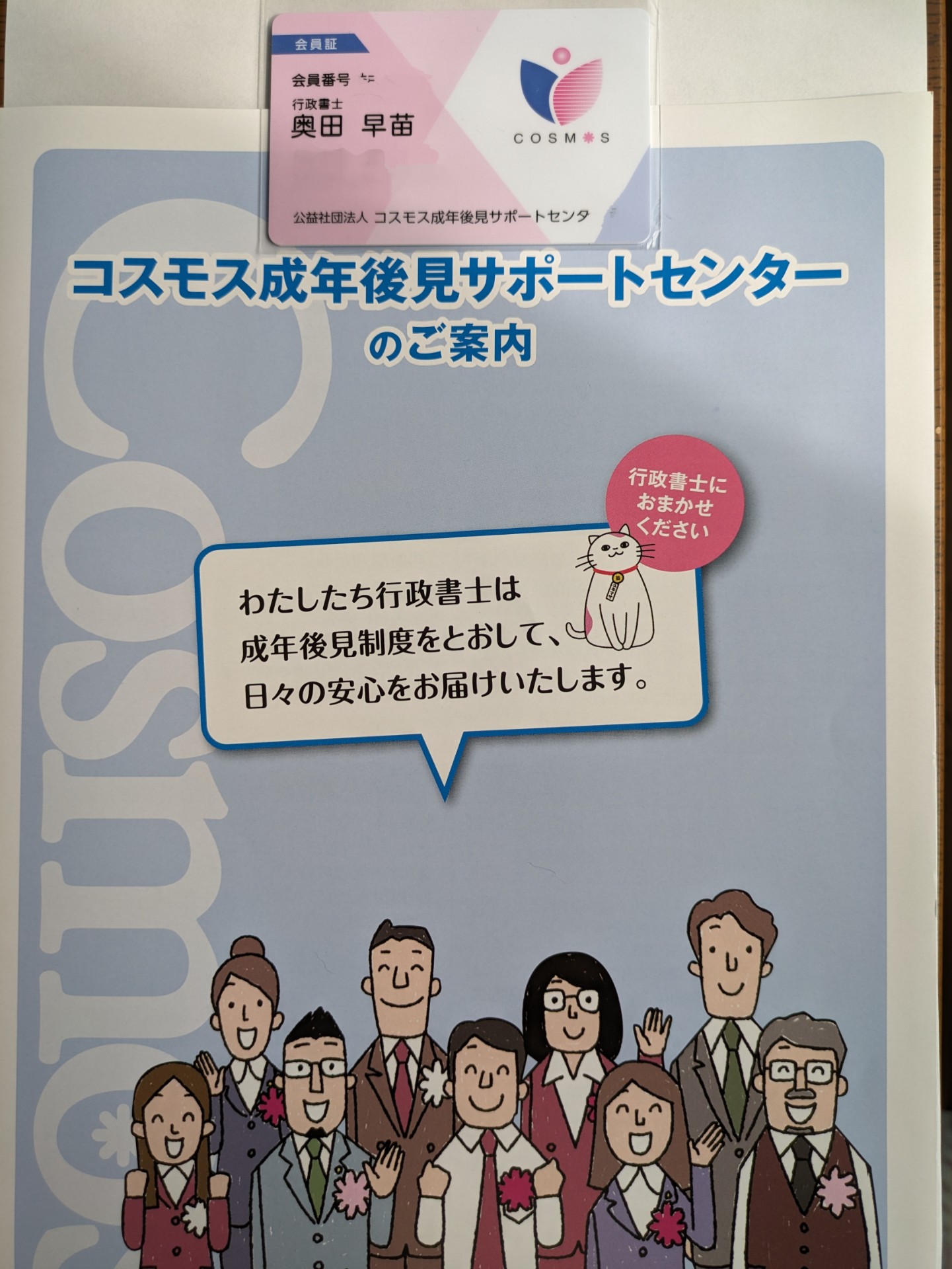
- 「はじめまして、後見人です!」 その④
- 今回は後見申立てにの際に大きなポイントとなる二つ目、「申立人」についてです。<div>前回の例を引き続き使い説明していきます。</div><div>Aさんの身上監護と財産管理のため、法的な代理人である後見人をつけるとなった場合、家庭裁判所に後見申立てをする必要があります。この「申立てをする人」、つまり申立人は誰が担うのか、がポイントになります。</div><div>申立ては、誰もができるわけではありません。例えばAさんの友人や近隣の方が、「Aさんには後見人が必要だから!」と自らAさんの為に一肌脱ごうと考えても、民法に照らすとそれはできません。「民法7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、…の請求により、後見開始の審判をすることができる」(一部を抜粋)と定められています。つまり、Aさんの配偶者か、四親等内の親族、またはAさん自身が申立人となる必要があります。Aさんの場合、四親等以内の親族にあたる、妹さんやそのお子様がいらっしゃいますので、この方々のご協力があれば、民法上申立人になることはできます。しかし、後見の申立ての為の準備は1日2日でできるものでは到底ないのが現状です。まず申立てに必要な書類を揃えるところから始まりますが、前回説明した医師の診断書は絶対ですし、その他に、申立書や申立事情説明書、財産目録、収支予定表などの書類作成が必要で、これらの書類の根拠となるような公的な書類(例えば、戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明、通帳のコピー等)を関係機関に請求する必要もあります。私は一度、私の父親の為にもし申立てをするとしたら、という前提で書類を作ってみたのですが、その膨大な量に心が折れそうになりました。また、自分の父親のことはたいてい分かっているから大丈夫と軽い気持ちで書き始めたのですが、学歴や職歴など過去の細かい経歴にまで触れる必要があり、また父の財産の内容や普段の生活における収支なども把握しきれておらず、これを申立人一人でこなすことは無理だと感じました。そして申立ての為には決められた手数料を支払う必要もあり、お金がかかります。前後しますが、申立ての為の書類作成や申立ての手続き自体を専門家に依頼すると数十万円の報酬もかかってきます。申立の際に、これらの費用をAさんの財産から支出することを請求する旨を付記することはできますが、申立人の心理的、物質的な負担はやはり大きくなります。</div><div>また例えばAさんに親族がいたとしても、様々な事情からAさんとの関りを拒まれ、申立人にはなりたくないという方もいらっしゃるかもしれません。では、Aさんに四親等以内の親族がいない場合はどうなるのでしょうか。実は申立ての中には、「首長申立て」というものもあります。これは本人の居住する市町村長が公の立場で申立人となるものです。市町村ごとに首長申立ての対象になるかの条件は異なりますが、実は令和5年度の申立のうちの約23%がこの首長申立て案件になっています。要因は様々考えられますが、おひとりさまの高齢者の増加、親族関係の希薄化などが挙げられます。</div><div>本人の身上監護、財産管理の為に後見申立てが必要となった場合、申立人が必ず必要となりますが、その役目を誰が担うのか、は大きなポイントです。</div><div><br></div><div>今回は前回に続き、後見の申立てから選任までのうち、「申立におけるポイント」のお話でした。</div><div>次回は、「はじめまして、後見人です! その⑤ 後見人には誰がなる?」のお話です。</div><div><br></div>
-
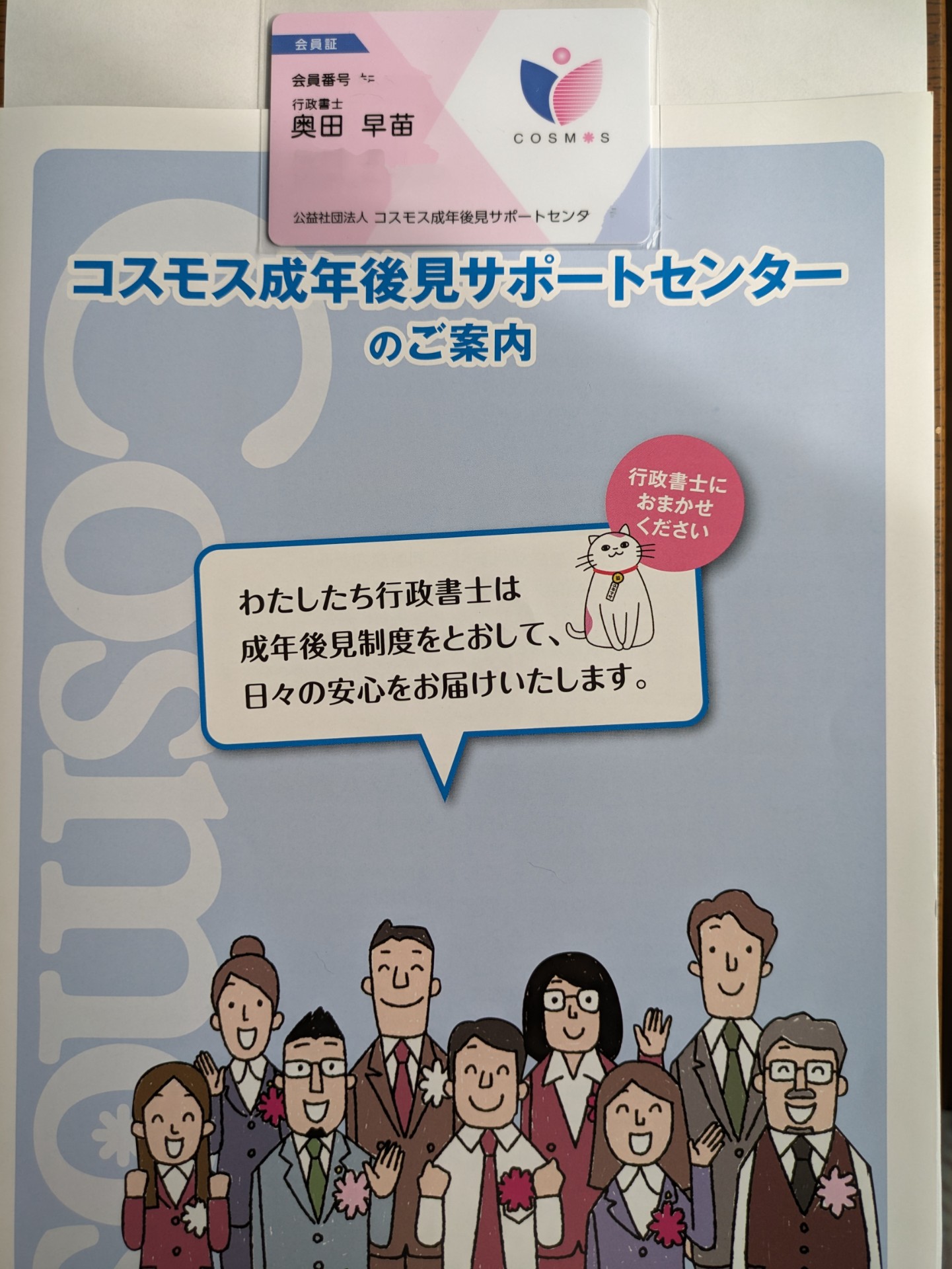
- 「はじめまして、後見人です!」 その③
- 今回は、後見の申立てから選任まで~後見申立てのポイント~を説明したいと思います。<div>分かりやすく、「認知症を患い、おひとり暮らしが困難となった高齢者のAさん」を例にあげてご説明します。<span style="text-decoration:underline"></span><div>Aさんは長年ご自宅にておひとり暮らしをされてきましたが、今回友人の一人からご様子がおかしいと行政に情報が寄せられ、調査の結果、認知症様の症状がかなり進行しており、すぐにでも公的な介護福祉支援を受けることが望ましく、また、自宅を含めた不動産や預貯金といった財産の管理も必要であることされました。Aさんには結婚歴がなく、お子様もおらず、妹さん(以下Bさん)がいらっしゃいますが遠方に住んでおり、Bさん自身も高齢で家族からの介護を受けており、すでにAさんのお世話をすることが困難な状況、Bさんにはお子様がいらっしゃいますが、とてもAさんの介護まで担うことはできないとの回答でした。こうなると、Aさんの身上監護、財産管理をAさんやAさんの家族親族に代わって行う後見人の申立てをすることを検討する必要が出てきます。</div><div><br></div><div>申立てをするのにまず必要になり、かつ大きなポイントになるのが、</div><div>1「医師の診断書」と、2「申立人」です。</div><div><br></div><div>今回は1について。</div><div>後見の申立てに必要になる書類は膨大にあります。申立書の書式は決まっていますが、それに添付する書類も官公署に請求したり、自ら作成したりする必要になります。その添付書類の中で、絶対に外せないのが、「診断書」です。逆にいうと、この診断書がなければ、申立てはできません。(家庭裁判所に受理されません)</div><div>ではこの診断書を書くのは誰か?当然「医師」になるのですが、このAさんの場合、「認知症であることが原因によって意思能力や判断能力を欠いている」という診断がされる必要があります。医師は精神科や神経内科など頭や心を専門にする医師でなくても構いません。最初に相談すべきは、やはりかかりつけ医です。しかし、ここで時々思わぬ壁にぶつかることがあります。あくまでも私の経験ですが、医師に診断書を依頼したが、「(診断書を)書けないと言われてしまった」という相談を受けることが時々あるのです。「うちは内科だから認知症かどうかの診断はできない」「検査ができないから」という実質的な理由なこともあれば、「この人は後見をつけるような重度の認知症ではないから」という判断や診断に基づく理由をあげられることもあります。私も長年医療の現場で働いてきましたが、後見申立てに関する診断書に限らず、医師が診断書を書く、ということは、大きな判断と責任をともなうことになります。私が以前に働いていた医療機関の院長は「診断書は医師の「全て」を込めて書くもの」と仰っていました。専門知識をもって書いた1枚で、その患者さんの権利や義務が確定し、生活や人生を変えることもある、だから真実しか書けない、と。先ほども触れた通り、家庭裁判所は、Aさんに後見が必要かどうかまず医師の診断書を参考にします。申立てを経て後見人がついた場合、後見人には大変大きな権限や裁量が認められ、たとえAさんの家族や親族でも、後見人を無視してAさんの身上監護や財産管理を行うことはできません。そうなると、ケースによっては、最初に診断書を書いた医師が家族や親族から思わぬバッシングを受けることにもなりかねないのです。(そんなことがあってはいけないと個人的には思うのですが)</div><div>医師の診断書を用意することは、申立には絶対条件になりますが、様々な事情、状況から、書いてもらえない、または書いてもらえる医師がいない、という壁にぶつかることもあるのが現状です。</div><div><br></div><div>今回は後見申立て時のポイントとして、「医師の診断書」をあげました。次回は申立て時のポイント、2申立人にフォーカスしたいと思います。</div></div>
-
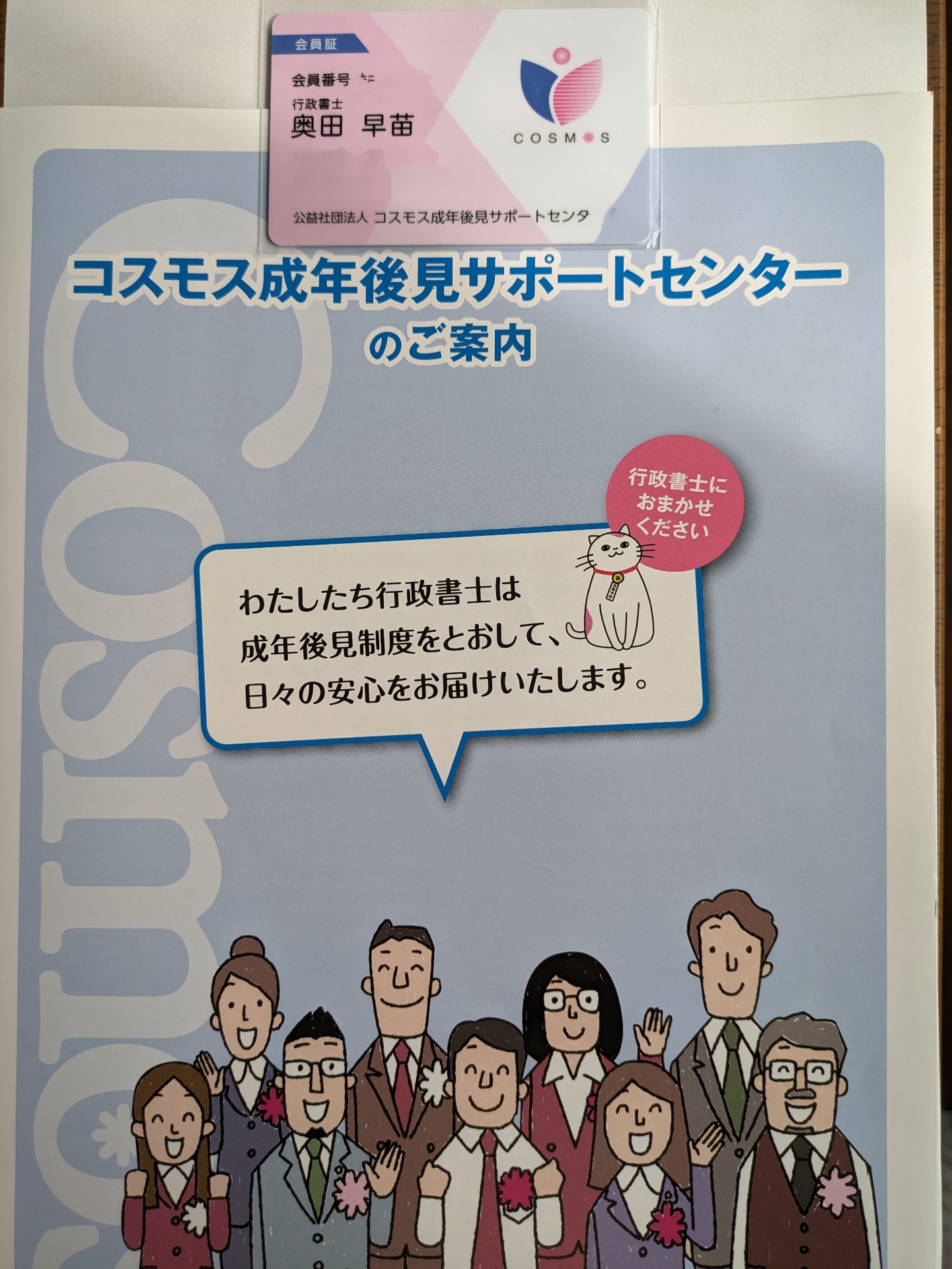
- 「はじめまして、後見人です!」 その②
- <div>前回に続き、後見制度をテーマとしたお話の続きです。</div><div>そもそも「後見」って何でしょうか。「後見」を百科事典で調べてみると、「背後にひかえて世話をすること、うしろだて」とあります。では、民法でいう後見は、どんな方に対して行うものでしょうか。ここからは皆さんにイメージしていただきながらお話をすすめたいと思います。もし認知症が理由で介護が必要な状態になった時、症状や状況にもよりますが、衣食住において、どなたかからの何らかのサポートが必要になります。たとえば家族と一緒に住んでいる場合、家族がその担い手になるケースもありますが、家族だけで介護の全てを負担することは、現実的に困難なことも出てきます。そんな時使える・備える制度として介護保険制度があり、介護度に応じて様々なサービスを受けることができます。では実際に介護サービスを受けるために必要な手続きや費用の支払いは、どなたが行うことになるでしょうか。皆さんの中で、真っ先に思い浮かぶ方はいらっしゃいますか。息子さんや娘さん、お嫁さんやお孫さんなど、家族や近しい親族が動いてくれるという方もいらっしゃると思います。しかし、結婚歴がなく、お子さんもいない、兄弟姉妹がいるが高齢ですでに頼れる状態ではない、中には様々な事情から、近くに家族や親族がいても頼れない、連絡もとれない、という方もいらっしゃるのも現実です。ではそのような状況にある方が、誰からの何の支援も受けず、生活を続けていくとしたらいかがでしょうか。これは実際にあった例なのですが、おひとり暮らしの高齢の方のご近所さんから行政へ、「最近様子がおかしい、話の辻褄が合わない、身なりが乱れている、自宅に不特定多数の人が出入りしている」等の情報提供があり、自宅訪問したところ、認知症がかなり進行した状態で、食事や保清もできておらず、また、不当に高額な代金で不要な自宅内のリフォームといった契約をさせられ預貯金をだまし取られている被害に遭っていた、ということが判明しました。認知症という病気は進行度や症状も様々ですが、ある程度進行すると、意思能力や判断能力が衰え、通常認知症ではない方が普段何気なくやれている、やっている判断や選択が正しくできなくなります。この例の方のように、自分の身の回りのことをすることが困難になったり、お金や貴重品など生きていくために必要な財産の管理も困難になったりします。では、この方が必要な支援を受けるにはどうしたらいいでしょうか。先に書いた通り、介護サービスを受けるためには様々な手続きが必要になり、また費用の支払いも必要です。しかし、この方のようにそれを担う家族や親族がいない場合は、第三者が行うことになりますが、契約や申し込み、お金の管理や支払いといった法律行為を行うことは責任がともないますし、お金が絡めば思わぬトラブルに陥ることもあるかもしれません。そこで、必要になるのが法的な代理人である、「後見人」です。つまり、後見人は、意思能力や判断能力が不十分な方や欠いている方の、身上監護と財産管理を目的として法律行為を行う権限を与えられた代理人ということになります。<br></div><div>よく「後見人って何するの?」とか、「なんで後見人が要るの?」と聞かれることがあります。後見人が必要になるケースは様々ですが、意思能力や判断能力に困難が生じている方に必要な身上監護と財産管理が後見人の業務となります。</div><div><br></div><div>今回は後見人が必要になるケースと後見人の業務についてのお話でした。</div><div>次回は、「はじめまして、後見人です! その③ 後見人が選任されるまで(申立てから審判確定まで)」のお話になります。</div>






